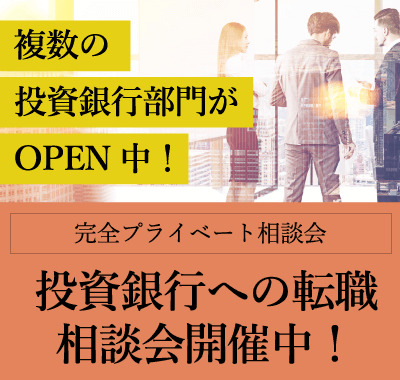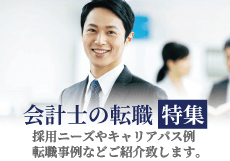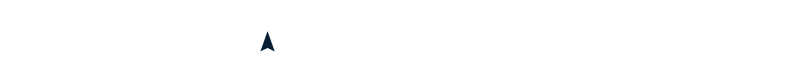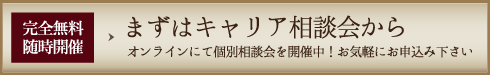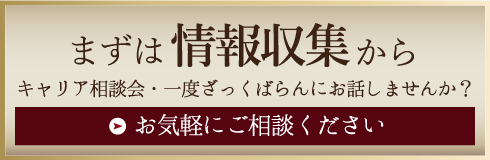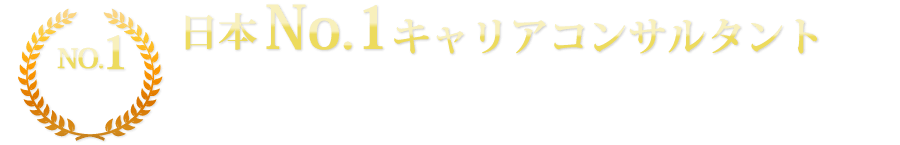銀行員の仕事はなくなる?将来性をデータと事例で徹底解説【2025年最新版】
「銀行員は将来なくなる職業なのか?」
そんな疑問を抱える人が増えています。
AIやフィンテックの進化、デジタル化の波の中で、銀行業界は今、かつてない大きな転換期を迎えています。
本記事では、銀行員の仕事内容や役割を正しく理解したうえで、業界の現状や変化の兆し、将来性のある職種や必要なスキル、さらには転職の可能性までを徹底的に解説します。
銀行を目指す方、働いている方、キャリアを考えるすべての方へ向けた2025年最新版の完全ガイドです。
銀行への転職をお考えの方は、ぜひ弊社ムービンにお問い合わせください。
銀行員の仕事内容と役割を正しく理解しよう
銀行員というと、「お金を預かる仕事」「ATMや窓口で働く人」といったイメージを持つ方も多いかもしれません。しかし実際の仕事内容は非常に多岐にわたります。ここでは、銀行員の基本的な役割と業務内容について整理しておきましょう。
銀行の仕事は、大きく分けて以下のように分類されます。
預金業務
- 普通預金、定期預金などの口座開設・管理
- 入出金、振込、口座解約などの手続き対応
融資業務(貸出業務)
- 企業や個人に対するローンの審査・契約
- 不動産ローン、自動車ローン、教育ローンなど
為替業務
- 振込・送金業務(国内・海外)
- 外貨両替、外国送金のサポート
投資信託・保険などの金融商品販売
- 個人向け資産運用の提案・販売
- ニーズに応じた商品選定とコンサルティング
法人営業
- 企業の資金繰りや経営支援
- M&A、事業承継、海外進出支援など
企画・本部業務
- 経営企画、リスク管理、マーケティング、IT部門など
- 店舗戦略や新規サービス開発にも関わる
これらの業務を通じて、銀行員は「社会の資金の流れを支える」重要な役割を担っています。特に企業との関わりは深く、地域経済を支える存在としての責任も大きい職業です。
銀行員は一般的に次のような特徴があります:
年功序列の組織文化
転勤が多い
コンプライアンス遵守が厳しい
安定した給与体系だが、昇給ペースは遅め
こうした特徴から、「安定しているが柔軟性に欠ける」「保守的な職場」と言われることもあります。
このように、銀行員の仕事は単なる「窓口業務」だけでなく、幅広い金融知識と高い倫理観、顧客対応力が求められる専門職なのです。
銀行業界の現状と変化の兆し
ここ数年で銀行業界を取り巻く環境は大きく変化しています。低金利時代の長期化、少子高齢化、地域経済の縮小、フィンテック企業の台頭など、複数の要因が同時に銀行業に影響を与えています。
低金利の継続
→ 貸出業務の利ざやが縮小し、銀行の収益が圧迫されています。
人口減少による市場縮小
→ 地方銀行を中心に顧客数・預金残高ともに減少傾向。
デジタルバンキングの普及
→ ネットバンク・アプリを通じた顧客対応が中心に。店舗来店が激減。
競合の多様化
→ メガバンクだけでなく、SBI、楽天銀行、PayPay銀行などのネット専業銀行が台頭。
以下のような変化が顕著です。
メガバンク(三菱UFJ、三井住友、みずほ)による数万人規模の人員削減計画
地方銀行同士の合併・経営統合の増加
支店の閉鎖・無人化・共同店舗化の加速
営業職の役割見直し(対面営業からデジタルコンサル型へ)
銀行業界は、構造そのものが大きく揺らいでいるタイミングにあります。つまり、「かつての安定業界」ではなくなっているのが実情です。
銀行員の将来性が不安視される理由
銀行員の将来性については、以前は「安定・高収入・社会的信用がある職業」として人気が高い仕事でした。しかし近年、このイメージは大きく揺らいでいます。特に若手社員や就職活動中の学生の間では、「本当に銀行に将来はあるのか?」という不安が広がっています。では、なぜ銀行員の将来が不安視されているのでしょうか。ここでは主な理由を詳しく見ていきます。
1. デジタル化による業務削減
インターネットバンキングやスマホアプリの普及により、来店客数が大幅に減少
窓口業務や振込・残高照会などが全てオンラインで完結可能
書類のデジタル化、電子契約の導入により、事務処理量が激減
この結果、従来必要だった「人手」が不要になってきています。
2. 競合の多様化とフィンテック企業の台頭
銀行業務の一部(送金、融資、資産運用)が、非銀行のフィンテック企業に奪われている
たとえば、住宅ローンや投資信託などもネット専業業者で完結するケースが増加
キャッシュレス決済、スマホ口座、AI診断など新サービスが次々登場
従来、銀行しか提供できなかった金融サービスの価値が相対的に下がっているのです。
これらの点から、銀行員という職業が、将来的に「安定・安心」ではなく、「変化に対応しなければ淘汰される職業」になりつつあることがわかります。
フィンテック(FinTech)とAIがもたらす影響
銀行業界の将来性を語る上で、無視できないのが「フィンテック(FinTech)」と「AI(人工知能)」の急速な進化です。これらは銀行業務のあり方を根本から変えつつあり、「人間の銀行員が必要とされなくなるのでは?」という懸念の中心にもなっています。
ここでは、フィンテックとAIが具体的にどのように銀行業務に影響を与えているのかを解説します。
フィンテック(FinTech)とは?
「フィンテック」とは、「Finance(金融)」と「Technology(技術)」を組み合わせた造語で、最新のIT技術を使って新たな金融サービスを提供する企業や仕組みを指します。
以下のように、従来銀行員が担当していた業務の多くがフィンテックに代替されつつあります。
業務領域
従来の担当
現在の代替サービス
口座開設
窓口・営業
オンラインバンキングで即日開設可能
送金・振込
窓口・ATM
アプリで24時間対応(手数料も低い)
投資提案
資産運用担当者
AIロボアドバイザーが自動運用提案
融資審査
法人・個人融資担当
自動スコアリングで最短数分で審査
財務管理
コンサル部門
自動連携されたクラウド会計ソフト
つまり、「人を介さないサービス」が主流になってきており、銀行員の存在感が薄れてきているのです。
さらに、AIの導入により以下のような業務が自動化されています。
融資の与信審査
→ AIによるスコアリングで、数秒でリスク判定
チャットボットによる顧客対応
→ 24時間対応の自動応答システムが窓口業務を代替
RPAによる事務作業の効率化
→ 書類処理・転記作業を自動化し、人手を削減
不正取引検知システム
→ AIが異常な取引をリアルタイムでモニタリング
市場分析や資産運用のアドバイス
→ 数百万件のデータを瞬時に解析し、最適解を提示
特に三菱UFJ銀行やみずほ銀行では、AIやRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)の導入が進んでおり、事務作業の大部分が機械に置き換えられつつあります。
こうした動向を踏まえると、今後の銀行は以下のような姿に変わっていくと予測されます。
店舗数は大幅に削減
多くの手続きはオンラインまたはアプリ完結
営業職・事務職は縮小し、高度専門職だけが残る
「人がいない銀行」が当たり前になる
つまり、「多くの人が働く大きな銀行」から、「テクノロジーが中心のスリムな銀行」への変化が加速しており、旧来の銀行員像とは大きく異なる未来が訪れようとしています。
実際に進むメガバンクの人員削減と再編
「銀行員の仕事がなくなる」と言われるようになった背景には、実際にメガバンクが大規模な人員削減や店舗再編を進めている現実があります。これは一時的なコスト削減ではなく、銀行業界全体が構造的な変革を迫られている証拠です。
各メガバンクは、以下のような方針を明確にしています。
店舗の統廃合(例:都心部の複数店舗を1つに統合)
完全予約制店舗の導入(待ち時間を排除)
支店内のキャッシュレス化(現金の取り扱い自体を縮小)
共同店舗化(他行とのシェア店舗)
無人店舗・遠隔相談窓口(テレビ会議・AIチャットボット対応)
この結果、2020年以降、全国で毎年100店以上の銀行店舗が閉鎖されています。都市部だけでなく、地方でもATMが撤去されるなど、「銀行のある風景」が変わりつつあります。
メガバンクの再編には明確な理由があります。
1. 収益構造の変化
低金利時代が長期化 → 貸出による利ざや収益が激減
法人向け融資市場も競争が激化し、利幅が縮小
外貨や証券など、リスク商品への依存度が上昇
2. デジタルへの投資シフト
テクノロジーに多額の投資(AI、フィンテック、クラウド化など)
人件費よりも、システム投資にリソースを集中
オンライン専業銀行との競争に打ち勝つため、デジタル化は避けられない
3. 業務の「見直し」ではなく「再構築」
単なる業務の効率化ではなく、「銀行の形そのものを変える」という方向性が強くなっているため、従来のスキル・役割では通用しなくなっているのです。
こうした動きは、現場の銀行員にとって大きなインパクトを与えています。
事務系・窓口系の職種は大幅な削減対象
一方で、IT・コンサル・法人営業の高度人材は中途採用の強化対象(実際に、採用数は右肩上がりで増加し続けている)
つまり、「すべての銀行員が不要になる」のではなく、「従来型の銀行員像」が再定義されているというのが現実です。
地方銀行の経営危機と統合の波
メガバンクの再編が進む一方で、地方銀行(地銀)はさらに深刻な状況に直面しています。地方の経済縮小、人口減少、若者の都市部流出などの影響を受け、収益の確保すら難しくなっている地銀も少なくありません。
地方銀行が経営危機に陥っている背景には、以下の3つの大きな要因があります。
1. 人口減少と地域経済の縮小
地方では高齢化と人口流出が深刻
地元企業の数も減少し、法人融資の需要が細る
2. 超低金利による利ざやの縮小
地銀の多くは預金と融資の利ざやで収益を上げるモデル
しかし長引く超低金利政策により、貸出金利が低下
3. デジタル対応の遅れ
都市部のネット銀行と比較してIT投資が遅れている
顧客は利便性の高いメガバンクやフィンテックへ流出
経営統合はコスト削減が目的であるため、当然ながら人員の整理や店舗の統廃合が行われます。
統合前に比べて支店数が半減するケースも
同じエリアにある支店同士を一本化
重複する事務業務の効率化により、人手を減らす方向へ
これにより、事務職や窓口担当の正社員が非正規化されたり、別業種への出向を命じられたりすることも増えています。
現在の状況が続けば、地方銀行は以下のような方向に進むと予想されています。
地域特化型サービスに特化(農業・観光支援、地域通貨など)
IT企業との提携強化(アプリ、ネット口座開設など)
行政・地元企業と連携した地域再生型金融
AI導入による少人数・効率運営体制の構築
つまり、従来の「預金と融資のモデル」から脱却し、地域と共に生きるための新しいビジネスモデルを模索している段階にあるのです。
銀行員の中でも将来性の高い職種とは
「銀行員の将来性が不安」と言われる中でも、すべての銀行職が一様に不要になるわけではありません。むしろ、これからの銀行には「生き残る職種」と「淘汰される職種」の二極化が進んでいくと考えられています。
まず、銀行員の職種を大きく以下の3つに分類します。
事務職系
窓口業務、後方事務、本部の処理部門など
→ 高度に自動化が進み、縮小傾向
営業職系
個人営業(リテール)、法人営業、外回りなど
→ コンサル型に進化すれば生存可能性あり
専門職系
金融商品開発、IT・DX推進、リスク管理、海外事業など
→ 成長分野であり、将来性が高い
将来性が高いとされる銀行職種5選
1. 法人向けコンサルティング営業
単なる融資提案ではなく、企業の経営課題を一緒に解決する「コンサル営業」へ進化中
事業承継、M&A、DX支援、海外進出など幅広い知識が求められる
「提案力」「課題解決力」が重要視され、今後も需要あり
2. 資産運用アドバイザー(IFA)
高齢化社会で増える「老後資金の管理」「相続対策」ニーズに対応
投資信託、保険、NISA、iDeCoなどを活用した提案が可能な人材が重宝される
証券会社や独立系ファイナンシャルアドバイザーとの競争も視野に入れた高度な専門職
3. リスク管理・コンプライアンス担当
金融庁による監督強化やマネーロンダリング対策(AML/CFT)が厳格化
ガバナンスや内部統制を強化する専門部署の人材が求められる
国際基準に対応できるスキルや資格(CAMS、CIAなど)があると尚良し
4. IT・DX推進担当(デジタルバンキング部門)
アプリ開発、システム設計、セキュリティ、ユーザー体験(UX)設計などを担う部門
既存の銀行業務とテクノロジーを橋渡しする役割を果たす
エンジニア経験やIT系資格(基本情報技術者、AWSなど)があると重宝される
5. グローバル業務・海外駐在員
海外進出を目指す企業を支援する法人営業
米国・アジア・欧州などに支店・駐在所を持つ銀行では、語学力と国際感覚が求められる
特に、ASEAN諸国との取引支援のニーズが高まっている
逆に将来性が低いとされる職種
窓口事務(口座開設・通帳発行など)
後方事務(帳票処理・伝票確認・照合作業など)
一般的な個人向け営業(商品説明型)
現金取扱担当(現金出納や集金業務)
これらはテクノロジーによる代替が進んでおり、すでに多くの業務が無人店舗・AIチャット・セルフ手続きに置き換えられています。
今後求められる銀行員のスキル
これからの銀行業界で生き残っていくためには、従来の「真面目で堅実」「決められた業務を正確にこなす」といった銀行員像から脱却し、変化に対応できる柔軟性と高付加価値なスキルが求められます。
本章では、今後の銀行員に必要とされる具体的なスキルと、それを支えるマインドセット(思考のクセ・姿勢)について詳しく解説します。
1. コンサルティング力(課題解決力)
顧客のニーズを聞き出し、潜在的な課題を発見
融資や金融商品の提案だけでなく、経営改善・資産形成全体を設計
「売る営業」から「支える営業」へ
※企業向けでは事業承継や資金繰りの支援、個人向けでは相続・老後設計の相談など
2. ITリテラシーとデジタルスキル
銀行システムの仕組みを理解する力
業務効率化のためのツール(RPA、Excel VBA、AIチャットなど)の活用
デジタルサービスに不安を持つ顧客に対し、説明・導入支援を行う役割
3. 金融+他分野の専門知識(クロススキル)
税務、会計、法務、経営など幅広い知識が求められる
企業再生、M&A、ファイナンス戦略など高度な知識があれば重宝される
金融だけで完結しない時代に対応する力
4. プレゼン・コミュニケーション能力
オンライン面談、ウェビナーなど非対面の営業スキルが重要に
社内外の関係者を巻き込んだ提案ができる人材が求められる
AIでは代替できない「人間的な信頼関係構築」がカギになる
5. データ分析・リスク感度
顧客データや取引履歴から行動傾向を読み取るスキル
不正取引の検知や融資判断などにもデータ分析が活用される
数字に基づいた判断力・リスク管理能力が重視される
現代の銀行員は、単なる「お金を扱う人」から、信頼と価値を提供するプロフェッショナルへの進化が求められています。
「過去の経験」よりも「これから学ぶ意欲」
「職務の幅広さ」よりも「深い専門性」
「所属する銀行のブランド」よりも「個人としての信頼性」
こうした視点を持つことで、将来性あるキャリアが築かれていくのです。
銀行員からの転職先とキャリアの選択肢
銀行員のキャリアは、これまでは「銀行内で定年まで働く」というのが一般的でした。しかし、業界の変化とともに、転職やキャリアチェンジを選択する銀行員が急増しています。
とくに、若手?中堅の層では、「今後の銀行に将来性はあるのか」「自分のスキルは他でも通用するのか」と不安を感じ、自ら動く人が目立つようになりました。
銀行員は、信頼性・コミュニケーション力・金融リテラシーが評価されやすく、以下の業種・業界に転職するケースが多く見られます。
1. コンサルティング業界(経営・財務)
銀行での法人営業経験がそのまま活きる
中小企業向けの事業支援経験、財務分析スキルが強み
2. FinTech・IT業界
金融知識をベースに、デジタルサービスを企画・運営する役割
銀行の仕組みに詳しい「ドメイン知識」が重宝される
プロダクトマネージャー、セールス、CS職などで活躍できる
3. 不動産業界・保険業界
融資担当の経験 → 住宅ローンや不動産投資関連業務に強み
FP資格を活かし、ライフプラン提案や資産形成のコンサルが可能
外資系保険会社や不動産ベンチャーへの転職も多い
4. 事業会社(経理・財務・経営企画など)
財務諸表を読み解く力、資金繰りの知識は企業経営に直結
特にスタートアップやベンチャーでは、資金調達経験が高く評価される
経営層との折衝経験もプラス評価に
5. 士業・専門職(資格取得後)
中小企業診断士、税理士、社会保険労務士などを目指して独立
銀行時代の人脈や信用が、顧客獲得の武器になる
FP1級、宅建などで副業やセミナー講師になる人も
「銀行員=優秀」と見なされがちですが、転職先でミスマッチが起こるケースも少なくありません。以下の点に注意が必要です。
【よくある失敗パターン】
「銀行ブランドが通じる」と思い込む(過信)
業務スピードや判断基準の違いに戸惑う
上下関係や社内政治に馴染めない
未経験職種への転職でスキルギャップに直面する
【対策】
「なぜ転職したいのか」を明確にする → 不満ベースではなく、キャリアの軸で考える
業界研究・職種理解を徹底する → 想像と現実のギャップを埋める
副業や社外活動で経験を積んでおく → いきなり転職より、段階的な準備も有効
銀行での経験は、たとえ業界を離れても貴重なキャリア資産です。なぜなら、以下のような特徴があるからです。
正確性・責任感・社会的信用を求められる厳しい環境での実務経験
コンプライアンスと高い倫理観が必要とされる職場での行動力
個人・法人を問わず、幅広い顧客対応スキルの獲得
つまり、銀行という「鍛えられる職場」で培ったスキルや姿勢は、異業種でも必ず活かせます。
これから銀行員を目指す人に伝えたいこと
ここまでの章で、銀行業界を取り巻く環境の変化や、将来性のある職種・スキル、さらには転職事情まで幅広く解説してきました。
最終章では、今まさに銀行員を目指そうとしている学生や若手社会人の方に向けて、業界の現実と、それでも銀行を選ぶべき理由、そして後悔しないための視点をまとめます。
「銀行員=オワコン」「AIに仕事を奪われる」といった極端な意見もありますが、これは一面的な見方にすぎません。たしかに、従来の「窓口業務中心の銀行員像」は大きく変わりつつあります。しかし、その変化の中には新しいチャンスも存在しています。
【変化の中で求められる新しい銀行員像】
デジタル時代に対応した顧客対応ができる人
単なる金融知識でなく、課題解決力を持つ人
地域社会や企業と深く関わり、価値を生み出せる人
つまり、銀行員という職業が「なくなる」のではなく、「再定義」されているというのが正しい理解です。
【銀行で働くことで得られる経験】
1. 高いビジネスリテラシーが身につく
財務諸表の読み方、資金繰りの知識、金融商品の仕組みなど
経営者や富裕層との対話から、リアルな経済の動きを学べる
2. 社会人としての基礎力が鍛えられる
正確さ、期日遵守、マナー、報告・連絡・相談の徹底など
あらゆる業界で通用する「社会人の土台」が築ける
3. 強い信頼と信用が得られる
銀行員という肩書は今でも一定の社会的信用がある
転職時にも「金融機関出身者」として評価されやすい
もしあなたがこれから銀行員を目指すなら、「なぜ銀行で働きたいのか?」「銀行で何を実現したいのか?」という問いに、自分なりの答えを持つことがとても重要です。
単に「安定していそうだから」「親が勧めたから」という理由では、環境が変化したときにモチベーションを保てません。
確かに、銀行員の仕事はこれからも大きく変わっていくでしょう。けれど、それは悲観すべきことではありません。むしろ今の銀行業界は、過去にないスピードで新しいビジネスが生まれ、チャンスが広がっている場でもあるのです。
あなた自身が「与えられた業務をこなす人」ではなく、「価値を生み出すプロフェッショナル」として成長できるなら、銀行というフィールドは非常に魅力的です。
変わりゆく銀行の中で、どんな銀行員になりたいのか。
それを真剣に考え、行動する人だけが、将来も必要とされる人材になれるのです。
【まとめ:銀行員の将来性は「変化にどう向き合うか」で決まる】
銀行員の仕事は変化しているが、なくなるわけではない
フィンテック・AIの進化で、求められるスキルもマインドも進化している
専門性・提案力・デジタルリテラシーがこれからの鍵
転職やキャリアチェンジの選択肢も豊富にある
これから銀行員を目指す人も、目的を持てば大きく成長できる
お申込み方法
すでに弊社にご登録の方は担当コンサルタントにお問い合わせください。
ご登録頂いてない方は、こちらからお申し込みください。お申込み後、弊社コンサルタントよりご連絡いたします。ご応募お待ちしております。










 初めての方へ - 転職を検討される金融業界の方へ【キャリアの考え方】
初めての方へ - 転職を検討される金融業界の方へ【キャリアの考え方】