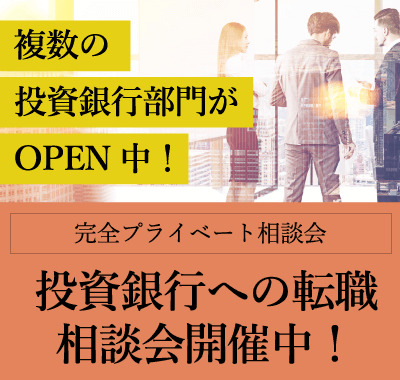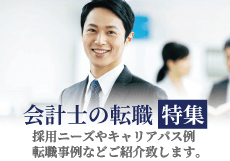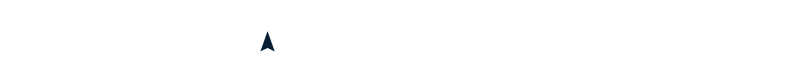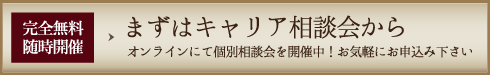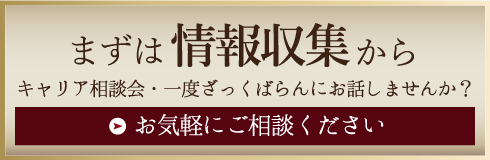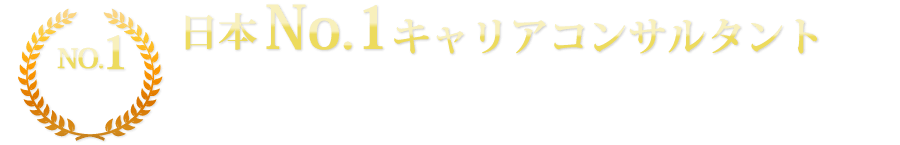M&Aのプロセス

買い手にとってのM&Aプロセスにおける各ステージ
財務DDとの関連性も含めながらご紹介致します。
M&A戦略の策定
マーケット、生産拠点、人材の確保、技術取得など、M&Aを実施する目的は何か、KPIを明確にすることから始めます。M&Aの実施目的とその成功の意味は一様ではないが、実施する目的は買収によるシナジーの最大化、株主価値の最大化にあるはずです。
戦略が策定されると実際に実行するプロジェクトチームが組成され準備が進められます。
ここで、投資アドバイザーや、弁護士、公認会計士・税理士など、社外のアドバイザーや専門家の活用の可能性が検討されます。
買い手が社外アドバイザーや専門家を利用する際の留意事項としては、何を依頼し、期待するのかを明確にしたうえで、意思決定者である自社のプロジェクトリーダーが主体性を持ってプロジェクトを進めることです。そうでなければ、アドバイザーや専門家の意見に振り回されてしまい、満足の行く結果が得られない可能性があります。
ターゲットの特定
買い手が候補企業を選定して買収の提案をする場合と、売り手もしくはその投資アドバイザーから買い手に対して売却提案がなされる場合とがあります。
買収ターゲットを選定する場合の手順として、
・自社の戦略に沿った選定基準を設定し、その基準に合致する候補をリストアップする。
・リストアップされた候補企業に関わる情報を収集し、さらに詳細な選定基準を設定し、絞り込む。
・上記で絞り込まれた候補企業の分析・検討を行い、最終ターゲットを決める。
相手先に対する買収は申込みは、買い手自身が行う場合と、投資アドバイザーを通じて行う場合があります。
接点のないターゲットに対しては、相手先の取引銀行や、証券会社、あるいはネームバリューのある投資アドバイザーを通じて行った方が交渉がスムーズに進む可能性があります。
事前検討
ターゲットを絞り込んでいく中で、または特定化されたターゲットに対して、予備調査(財務分析)を行います。
ターゲットに接触する前のノンアクセスの状況で、財務調査を行う目的は、予想されるシナジーや暫定的な価値評価、ストラクチャーなどに基づいて検討することによって、提示する買収の基本的条件を決めることにあります。
価値評価とストラクチャーは、M&Aの成否に直接的に影響を及ぼすことになる最重要事項であり、事前検討後、フルスコープDDを経て、再検討・調整を行い最終決定をしていきます。
基本合意書締結
特定されたターゲットに対して、買収の申入れをして交渉がスタートします。ここで買い手側から買収価格やストラクチャーなど基本条件を提示します。
これは両社のトップ会談によって行われることもあれば、買い手の代理人として投資アドバイザーを通じて行う場合もあります。
基本合意した場合、両社間の理解を確認するため基本合意書を締結します。
基本合意書の基本条件は以下のような事項があります。
・買収範囲
・ストラクチャーと対価の支払方法
・買収価格
・スケジュール
・経営陣の処遇、従業員の継続雇用などの人事関連
・買い手の独占交渉権
・デューデリジェンスの実施
・合意書が法的拘束力を持たない旨
これは、合意文書であり、決まった項目等もありません。また、必ず作らなければいけないものでもありません。
ではなぜ、この合意書を締結するかというと
・早い段階で双方の意向を書面で確認できる
・DDについての売り手の協力体制が明示される
・一定期間、独占交渉権が得られる
・買収価格の上限を設定できる
など買い手にとってのメリットがあるからです。
どちらか一方が法的拘束力があるという位置づけで進んだ場合、スケジュールが大幅に遅れたり、DD実施後の交渉に柔軟性がなくなり、妥協点を見出すことが困難になる可能性があります。
日本企業同士で大型案件の場合には、会社内外への影響力が大きいため、DD実施後に基本合意を締結する場合もあります。
デューデリジェンス
基本同意書締結後、DD(デューデリジェンス)を実施するために、ターゲットの機密情報にアクセスするための秘密保持契約を行います。この契約の有効期限は1〜3年程度でディールが不成立になった場合、入手資料等の返還義務が明示されます。
秘密保持契約締結後、データルームが設置され関係書類の閲覧やターゲットのマネジメント層、従業員へのインタビューなど、ビジネス・法務・財務・人事・環境・ITなどさまざまな視点から調査が行われることになります。
DDの結果、検出された問題点や課題のことをディール・イシューといいます。ここで買い手は、この交渉を先に進めるかどうかという重大な決断を行うことになります。
ディール・イシューのうち、買収を断念せざるを得ないような問題をディール・ブレーカーといいます。もしDDによりディール・ブレーカーが検出され、解決策を見出せない場合にはそのM&Aは断念するしかありません。
交渉の継続を前提とした場合、ディール・イシューに対する対応策は
・買収価格への反映
・ストラクチャーの変更あるいは投資のタイミングの調整での対応
・買収契約書における表明・保証
の大きく3つに分類さえます。
買収契約書締結
DDの結果を受けて、売り手買い手、双方での最終的な交渉が行われ、合意した内容は法的拘束力をもつ最終的な買収契約書にまとめられます。
この契約書の草案は、通常法務DDを実行する買い手の弁護士が中心となって起草し、買い手のプロジェクトチームと公認会計士等の専門的なアドバイザーのコメントを受けて作成されていき、この草案をめぐって売り手、買い手間での激しい交渉が行われることになります。
交渉の中でも特に重要な論点となるのが、買収価格、ストラクチャーそして表明・保証条項です。なぜなら、DDの実施により浮かび上がってきた、ターゲットの問題点が集約されているからです。
交渉がスムーズに進んだ場合、DDの完了後から数週間から1ヶ月程度で買収契約書の締結に至りますが、交渉が難航すると締結まで数ヶ月から半年程度の期間を要する場合があります。
クロージング
買収契約書の規定するクロージング・コンディションを満たすことを条件に、規定されたに維持に対価の支払いと目的物の移転(資産もしくは株式の受け渡し)が完了して取引は完了します。
買収価格決定のベースとなるターゲットの価値評価は、クロージング日までの期間におけるターゲットの業績変動などの状況の変化を反映した買収価格の調整の余地を残しておく必要があります。
買収契約書の条項に記載する「買収価格調整」という目次があるのですが、これが適用されるとクロージングの後に一定の方法により買収代金の一部が清算されます。
買収契約書締結後、買収価格調整の要否を確認するために最終のDD(クロージングDD)が実施される場合があります。このような場合には、契約書に誰がどのような方法でDDを実施するかも詳細に記述されます。
新体制がスタートした第1日目をDay1と呼びます。
ここから先は、新体制の下でシナジーの最大化を目指した経営統合活動が行われますが、これは、Day1以降に開始されるのではなく、実行段階からDay1に向けての準備を始めます。
さまざまな視点から総合的DDにより検出された統合上の課題をDay1に向けて落とし込み、ビジネスに支障をきたすことなく、周到な準備を行います。
統合(PMI: Post Merger Integration)
新体制がスタートした第1日目をDay1と呼びます。
ここから先は、新体制の下でシナジーの最大化を目指した経営統合活動が行われますが、これは、Day1以降に開始されるのではなく、実行段階からDay1に向けての準備を始めます。
さまざまな視点から総合的DDにより検出された統合上の課題をDay1に向けて落とし込み、ビジネスに支障をきたすことなく、周到な準備を行います。
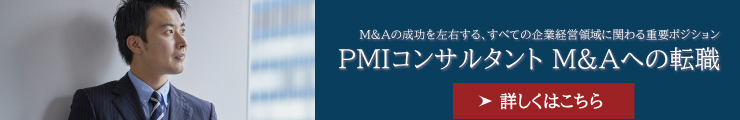
M&Aへの転職ならムービンにご相談下さい
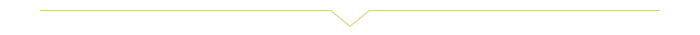
転職サービスはすべて無料となっております。
ムービンではお一人お一人に合わせた転職支援、そしてご自身では気づかれないキャリアの可能性や、転職のアドバイス、最新の情報をご提供致します。
- 大手M&Aアドバイザリーファーム(FAS)への支援実績No.1
- 29年以上の転職支援実績と圧倒的なノウハウ
- 10,000名以上のM&Aポジションへの転職サポート
M&Aへの転職ならムービンにご相談下さい
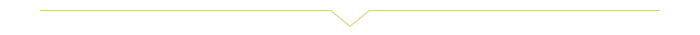
転職サービスはすべて無料となっております。
ムービンではお一人お一人に合わせた転職支援、そしてご自身では気づかれないキャリアの可能性や、転職のアドバイス、最新の情報をご提供致します。
- 大手M&Aアドバイザリーファーム(FAS)への支援実績No.1
- 29年以上の転職支援実績と圧倒的なノウハウ
- 10,000名以上のM&Aポジションへの転職サポート
M&A転職 - MENU -
M&Aについて


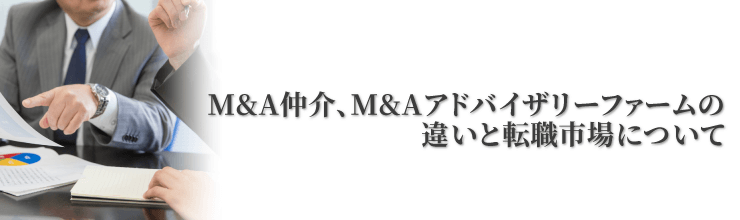


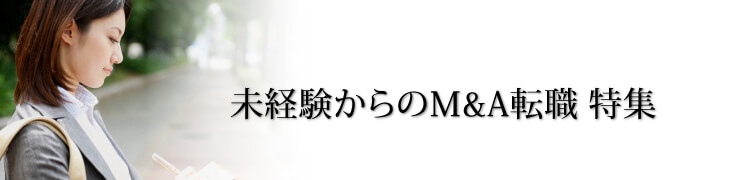
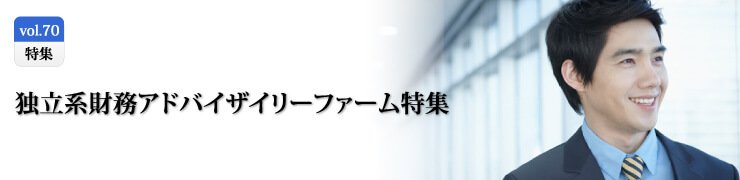
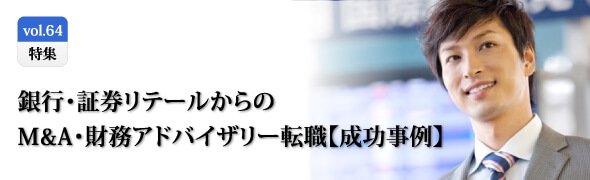

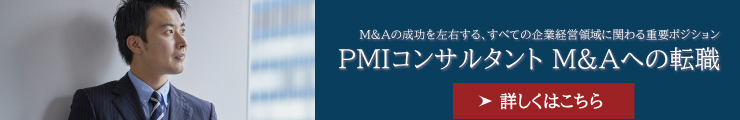
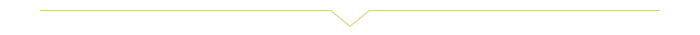
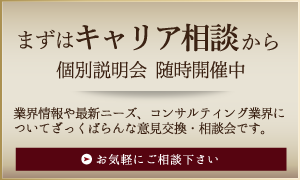
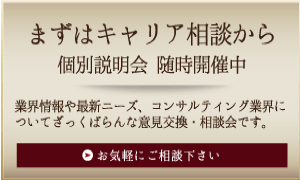










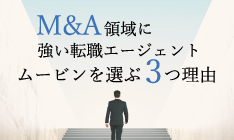
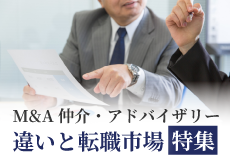
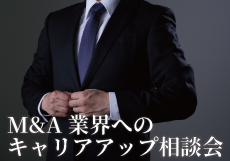
 初めての方へ - 転職を検討される金融業界の方へ【キャリアの考え方】
初めての方へ - 転職を検討される金融業界の方へ【キャリアの考え方】