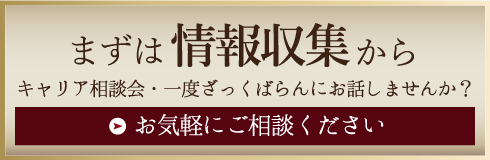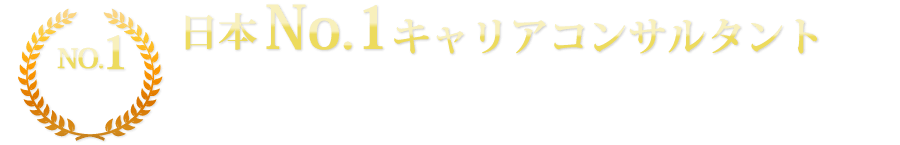��L1���̍��i���͂������Z���H�ŐV�f�[�^�Ɠ�Փx��O�����I
��L1���̍��i���͂ǂꂭ�炢�H�y�ŐV�f�[�^�z
��L1���́A������L����̒��ł��ł���Փx���������i�����ł��B���̍��i���́A���̋��Ɣ�r���Ă����|�I�ɒႭ�A��N10���O��Ő��ڂ��Ă��܂��B�����ł́A�ŐV�̍��i���f�[�^�ƁA�ߋ��Ƃ̔�r�����ƂɁA��L1���̍��i�̓�������Ă����܂��傤�B
�N�x�ʂ̕�L1�� ���i���i����5�j
| ���{�� | ���{�N�� | �\���Ґ� | �Ґ� | ���i�Ґ� | ���i�� |
|---|
| ��168�� | 2024�N6�� | 9,450�l | 6,512�l | 750�l | 11.5% |
| ��167�� | 2023�N11�� | 10,203�l | 7,132�l | 781�l | 10.9% |
| ��166�� | 2023�N6�� | 9,876�l | 6,984�l | 705�l | 10.1% |
| ��165�� | 2022�N11�� | 10,452�l | 7,321�l | 683�l | 9.3% |
| ��164�� | 2022�N6�� | 10,112�l | 7,104�l | 812�l | 11.4% |
���f�[�^�o�T�F���{���H��c���i������L��������T�C�g�j
���i�����猩���邱��
��N10���O��ň��肵�Ă���
�� �������x���Փx�̑傫�ȕύX���Ȃ��A���̓�Փx���ێ����Ă��邱�Ƃ��킩��܂��B
�N�ɂ���Ď�̃u���͂��邪�A�傫�ȕϓ��͂Ȃ�
�� ���̓�������A�҂̏����ɍ��E����镔�����傫���ƌ����܂��B
���̋��Ƃ̔�r�i2���E3���Ƃ̈Ⴂ�j
| �� | ���i���i���ρj | ��Փx | ��Ȏґw |
|---|
| 3�� | ��40�`50% | ������ | ���Z���E���S�� |
| 2�� | ��20�`30% | ������ | ��w���E�Љ�l |
| 1�� | ��10%�ȉ� | ������ | �o�������ҁE�㋉�� |
��L1���́A�P�ɍ��i�����Ⴂ�����łȂ��A�w�K�͈͂̍L���E�L�q���̑����E�v�Z�̕��G�����e�����A���w�҂�Ɗw�҂ɂƂ��đ傫�ȕǂƂȂ��Ă��܂��B
��L1���̍��i�����Ⴂ���R�Ƃ́H
��L1���̍��i����10���O��ɂƂǂ܂��Ă���ő�̗��R�́A���̎����̓����ɂ���܂��B�����ł́A���3�̗v�����ڂ���������܂��B
�o��͈͂����ɍL���A���I
��L1���ł́A�ȉ���4�Ȗڂ��o�肳��܂��F
���ƕ�L
��v�w
�H�ƕ�L
�����v�Z
���ꂼ��ɂ����Đ��I�Ȓm���Ǝ��H�͂����߂��܂��B���ɉ�v����Ɖ�v�����ȂǁA���ۓI�ňËL���K�v�ȓ��e�������A���_�Ǝ����̗����ɑΉ�����K�v������܂��B
�L�q��肪�����A���ԂƂ̐킢�ɂȂ�
2���ȉ��ƈႢ�A1���ł͌v�Z�����łȂ��L�q�`���̖�肪�����o�肳��܂��B�܂�A�P�ɐ��m�Ɍv�Z�ł��邾���ł͑��肸�A�_���I�ɐ�������́E���{��́E��v�I�v�l�͂�����܂��B
����Ɏ������Ԃ� 3���ԁi90���~2���\���j �ƒ����ł����A���̃{�����[�������ɑ������ߎ��Ԃ�����Ȃ��҂������ł��B
�Ɗw�ł̍��i������A�r���ō��܂��₷��
��L1����2���܂łƂ͈Ⴂ�A�Ɗw�����ł͌��E�������₷�������ł��B���R�͈ȉ��̒ʂ�F
��发�̓��e������ŗ����Ɏ��Ԃ�������
�ߋ���̌X�������݂ɂ����A���H�͂����ɂ���
���`�x�[�V�����̈ێ�������A�r���ŗ��E���₷��
���̂悤�ȗ��R����A�p���I�Ɋw�K�ł�����i�\���Z�E�ʐM�u���Ȃǁj�����p����҂��L���Ƃ���Ă��܂��B
�����i�Ƃ̔�r�ł킩����
| ���i | ���i�� | ��Փx�i��ρj | �w�K���Ԃ̖ڈ� |
|---|
| ��L2�� | ��20�`30�� | ���� | ��3�`6���� |
| ��L1�� | ��10�� | �㋉ | ��6����?1�N |
| �ŗ��m�i��L�_�j | ��15���O�� | �㋉ | ��1�N?1�N�� |
���̕\������킩��悤�ɁA��L1���́u�ŗ��m�����̓o����v�Ƃ������郌�x�����ł��B
���i�����Ⴂ�̂́u�������x�v�ł͂Ȃ��u���͍��v
��L1���̍��i�����Ⴂ�̂́A�����Ď������s�����Ȃ̂ł͂Ȃ��A�������e�̃��x���������A���i��ɓ��B�ł���l�����Ȃ����Ƃ������ł��B
�������A�������w�K���@�ƌp���͂�����A�N�ɂł����i�̃`�����X�����鎑�i�ł�����܂��B
��L1�����i�ɕK�v�ȕ����ԂƊw�K����
��L1���́u���i��10���O��v�Ƃ������������������ʂ�A��������Ƃ����w�K���Ԃ��m�ۂ��Ȃ�����i�͓�������ł��B�����ł́A���i�҂̕��ϕ����Ԃ�A�Љ�l�E�w���ʂ̊w�K�X�P�W���[���̖ڈ����Љ�܂��B
���i�ɕK�v�ȑ������Ԃ̖ڈ�
��ʓI�ɁA��L1�����i�܂łɕK�v�Ƃ���鑍�����Ԃ� 600�`1,000���Ԓ��x �ƌ����Ă��܂��B
| �ڕW���x�� | �������� | �Ώێ� |
|---|
| �Œ�C�� | ��600���� | ��L2���̓��e���蒅���Ă���l���� |
| ���S�� | ��800�`1,000���� | ���w�҂�u�����N������l���� |
�Q�l�FTAC��匴�Ȃǂ̎��i�w�Z�̃J���L���������犷�Z�������ϒl�ł��B
�w�K���Ԃ̖ڈ��i�T10�`15���Ԋw�K�����ꍇ�j
| �w�K�X�^�C�� | �T������w�K���� | ���i�܂ł̊��Ԗڈ� |
|---|
| �w���i���ɏW���ł���j | 15�`20���� | ��6�`8���� |
| �Љ�l�i�d���Ɨ����j | 10�`12���� | ��9�`12���� |
| �ʐM�E�ʊw�u�����p�� | �J���L�������ʂ� | ��8����?1�N |
�w�K�̐i���ɂ͌l��������܂����A�u����1?2���ԁ{�T���ɂ܂Ƃ܂������ԁv���p�����邱�Ƃ���ł��B
���i�҂̐����猩��g���A���ȕ����ԁh
�Ɗw���i�҂̗�F�u�Љ�l�ŕ���2���ԁA�T��8���ԁB9�����ԂŖ�800���ԕ����܂����B�v
�ʐM�u�����p�҂̗�F�u���ʐM�u���̃X�P�W���[���ɏ]����10�����ԁB�g�[�^��900���ԂقǁB�v
���i�҂ɋ��ʂ��Ă���̂́A�u���X�̐ςݏd�ˁv�u�v��I�ȉߋ��≉�K�v�����ɂȂ��Ă���_�ł��B
���`�x�[�V�����ێ��̃R�c
�����ȒP�����ƂɖڕW��ݒ肷��i1�T�Ԃŗ��_�����d�グ��Ȃǁj
�����Ԃ̋L�^�A�v�����g���ĉ�������
SNS��w�K���ԂƂȂ����Čp���ӎ������߂�
���Ԃ����łȂ��u���v�������
��L1���́A�P�Ɏ��Ԃ���������i�ł��鎎���ł͂���܂���B�����̐[���E�A�E�g�v�b�g�i��艉�K�j�̗ʁE���K�̕p�x�����ۂ�傫�����E���܂��B
�t�Ɍ����A�������w�K�헪������A����ꂽ���Ԃł����i�͏\���\�ł��B
���i�����猩���L1���̓�Փx�ƈʒu�Â�
��L1���́A���i����10���O��Ƃ�������������킩��悤�ɁA���ɓ�Փx�̍������i�����ł��B�������A���ꂾ���Ɏ擾��̐M������]���������A��v�E�o���E��ڎw�����ɂƂ��Ắu�����ƃL�����A�̋��n���v�ƂȂ鎑�i�ł��B
�����ł́A�����i�Ƃ̔�r��Љ�I�ȕ]������A��L1���́g�����ʒu�h���q�ϓI�ɐ������Ă����܂��B
���̉�v�n���i�Ɣ�r������Փx
| ���i�� | ���i�� | ��Փx�i��ρj | �擾��̕]�� |
|---|
| ������L3�� | ��40?50% | ���僌�x�� | ��v�̊�b�m���Ƃ��ĕ]������� |
| ������L2�� | ��20?30% | �������x�� | �o���E�̍Œ�����Ƃ��čL���F�m |
| ������L1�� | ��10%�O�� | �㋉���x�� | ��v�̐��E�Ƃ��Ĉ�ڒu����� |
| �ŗ��m�i��L�_�j | ��15�� | �㋉���x���ȏ� | ���ƂƂ��ēƐ�Ɩ����� |
| ���F��v�m | ��10%�ȉ� | �ŏ㋉���x�� | ���Ǝ��i�A�č�����x�����\ |
��L1���́A�ŗ��m���v�m�Ɣ�ׂ���Ǝ��i�ł͂���܂��A��Ǝ����ɒ�������X�L�����ؖ��ł���g�����^�̏㋉���i�h�Ƃ��ďd��܂��B
��Ƃɂ�����]���E�L�����A�̍L����
��L1�����擾���Ă���ƁA��Ƃ���ȉ��̂悤�ȕ]�����₷���Ȃ�܂��F
�o���E��������ł̑���͐l�ނƂ��ĔF�������
��v�\�t�g�̓����E�^�p�A�A�����Z�Ή��ȂǁA���x�Ȏ����ɑΉ��ł���m��������Ɣ��f�����
�ŗ��m�����i���i�j�ɂ��������邽�߁A����ɏ�ʎ��i��ڎw����b�Ƃ��Ă����l������
�Q�l�F������L1�����i�҂́A�ŗ��m�����̎��i���܂��i�w��s��j�B
��L1���́g�����m���h�{�g���_�h�̗Z���������
2���܂ł͎�Ɏd��ƌv�Z�����S�ł����A1���ł́u��Ƃ̍����헪���v���j�܂ŗ������Ă��邩�v��������܂��B
�܂�A�P�Ȃ�L���\�͂ł͂Ȃ��A��v���g�ǂޗ́h�g���͂���́h���K�v�ɂȂ�܂��B
��Փx�̈ʒu�Â��܂Ƃ�
| �v�f | ���e |
|---|
| �w�K���� | �����i600?1,000���ԁj |
| �o��͈� | ���ɍL���i4�Ȗځj |
| �]�������ƊE | ��v�������A�o���E�����E�A����ƂȂ� |
| �L�����A���� | �]�E�E���i�ŗL���ɂȂ�\�������� |
| ���i���l | �����́{�����̐��E�ɂȂ���y��Ƃ��ėL�� |
��Փx�͍������A���l�͂���ȏ�ɍ������i
������L1���́A���i��10���Ƃ�����֎��i�ł���Ɠ����ɁA�����ł̐M�����E�L�����A�A�b�v���ʂ̍������i�ł�����܂��B
��Փx�̍����͊m���ł����A���ꂾ���Ɏ擾���邱�Ƃœ�����g�M�p�Ɖ\���h�͔��ɑ傫���Ƃ�����ł��傤�B
��L1���ɍ��i���邽�߂̕��@�Ƃ������ߋ���
��L1���́A�o��͈͂��L���A��Փx���������߁A�g���������@�h�Ɓg�M���ł��鋳�ޑI�сh�����ۂ�傫�����E���܂��B�����ł́A���X�^�C���ʂɁA���ʓI�Ȋw�K���@�ƒ�Ԃ̂������ߋ��ނ��Љ�܂��B
���@�@�F�Ɗw�ō��i��ڎw���ꍇ
�� ���̐i�ߕ��i��{�X�e�b�v�j
�C���v�b�g���i3?4�����j
�@���ƕ�L�E��v�w�E�H�ƕ�L�E�����v�Z�̊�b���w��
�@�� ���ȏ��Ɩ��W���Z�b�g�Ŏg���A���K�܂ł��Ȃ�
�A�E�g�v�b�g���i3����?�{�����܂Łj
�@�ߋ���E�\�z���Ŏ��H�͂�����
�@�� �{�Ԍ`���Ɋ���邽�߁A���Ԃ��v���ĉ������K���d�v
�� �Ɗw�����������ߋ��ށi���Ёj
| ���ޖ� | ���� |
|---|
| �X�b�L���킩��V���[�Y�iTAC�o�Łj | ���w�Ҍ����B�}���������킩��₷���B�S4�ȖڑΉ� |
| ���i�e�L�X�g���g���[�j���O�i������L1���j�yTAC�z | �Ɗw�҂̒�ԁB�{�����[�����߂����̌n�I�Ɋw�ׂ� |
| �悭�킩���L�V���[�Y�i�l�b�g�X�N�[���j | �����d���B��b�ł߂Ɍ����Ă��� |
�|�C���g�F���ׂẲȖڂœ����o�ŎЂő�����ƌ����I�Ɋw�K�ł��܂��B
���@�A�F�ʐM�u�������p����ꍇ
�� �ʐM�u���̃����b�g
�����̃y�[�X�Ői�߂���i�Љ�l�ɐl�C�j
�u�t�ɂ�铮�������������T�|�[�g
�Y��⎿��x�ŕs���_�����̂܂܂ɂ��Ȃ�
�� �������߂̒ʐM�u��
| �u���� | ���� |
|---|
| �X�^�f�B���O ��L1���u�� | �X�}�z�Ŋw�ׂ�I�X�L�}���Ԋ��p�ɍœK�B���i������ |
| �N���A�[�� | �g��펯���i�@�h�Ŏ��Z�w�K���d���B����x���[�� |
| TAC�E�匴 | ���i�w�Z�̉����B���ށE�u�`�E�T�|�[�g�S�Ă����i�� |
�\�Z�ڈ��F�ʐM�u����5��?12���~���x������B
�R�X�g��}�������ꍇ�́A������Ɓ{���Е��p���������߂ł��B
���@�B�F�ʊw�u����I�ԏꍇ
�w�K�y�[�X���u�t���Ǘ����Ă����
���`�x�[�V�������ێ����₷��
����E���K�T�|�[�g��������i����TAC�E�匴�j
�Љ�l�ɂ͂��n�[�h���������ʊw�`���ł����A�Z���ԂŊm���ɍ��i��ڎw�������l�ɂ͌��ʓI�ł��B
���i��ڎw�����߂́g���̃R�c�h
���Ȗڂ���ɂ��Ȃ�
�@���Ɂu��v�w�v�u�����v�Z�v�͋��ӎ������l���������߁A���߂̑���B
�ߋ���͍Œ�5�͔������K
�@���`���Ɋ���邾���łȂ��A�u�̗���v�ɒ蒅������B
�X�P�W���[�����ׂ������
�@�u���T���͐i�߂�v�ȂǒZ���I�ȖڕW��ݒ肷��ƍ��܂��ɂ����B
�����ɍ������w�K�X�^�C���{�M���ł��鋳�ނ����i�ւ̋ߓ�
��L1�����i�̂��߂ɂ́A�u�ǂꂾ�����Ԃ����������v�ł͂Ȃ��A�u�ǂꂾ���������Ďg�����Ȃ��邩�v���J�M�ł��B
�Ɗw�E�ʐM�E�ʊw�A������̕��@��I��ł��A��т������v��Ƌ��ޑI�т����i�ւ̓y��ɂȂ�܂��B
�]�E���������Ƃ������́A���Ѓ��[�r���܂ł��C�y�ɂ����k���������I
![����l����l�ɍ������]�E�x���A��C�L�����A�R���T���^���g���T�|�[�g](/finance/sp/img/spfootobititle.svg)

![���߂Ă̕��� - �]�E�������������Z�ƊE�̕��ցy�L�����A�̍l�����z](/finance/newimg/s_first2.jpg) ���߂Ă̕��� - �]�E�������������Z�ƊE�̕��ցy�L�����A�̍l�����z
���߂Ă̕��� - �]�E�������������Z�ƊE�̕��ցy�L�����A�̍l�����z

![M&A�ƊE�ւ̓]�E �L�����A�A�b�v���k��](/finance/newimg/b_ma3.png)
![�y�L�����A���k��z������s�ւ̓]�E���k��J�Ò��I](/finance/newimg/b_ibdseminar.png)
![������s�ւ̓]�E](/finance/newimg/sb_toshi.jpg)
![��v�m�̓]�E](/finance/newimg/b_accountant.png)


![�y���K�o���N����̓]�E��z��̓I�ȋƊE�E���](/finance/newimg/s_bank52.jpg)
![��v�m�̓]�E](/finance/newimg/under/under_accountant.jpg)
![�y�،����e�[���c�Ƃ̓]�E��z�ϋɓI�ɋ��߂�ƊE�E���](/finance/newimg/under/under_secu.jpg)

![�R���T���^���g�]�E�T�C�g](/it/img/site_consul.jpg)
![IT�R���T���^���g�]�E�T�C�g](/it/img/site_it.jpg)
![���Z�]�E�T�C�g](/it/img/site_finance.jpg)
![�g�D�l���R���T���^���g�]�E�T�C�g](/it/img/site_hc.jpg)
![�G�O�[�N�e�B�u�]�E�T�C�g](/it/img/site_post.jpg)
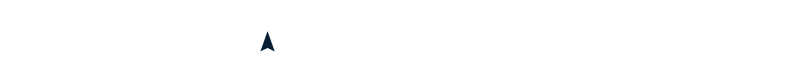



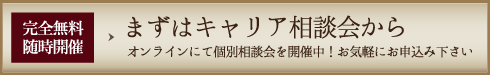
![���Z�]�E�̃��[�r��](/finance/sp/image/head.svg)