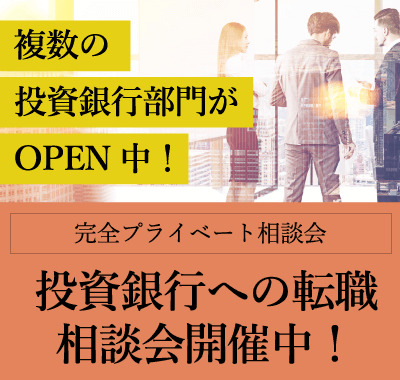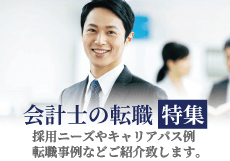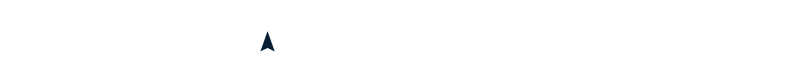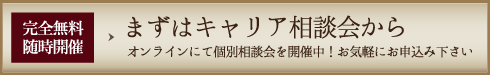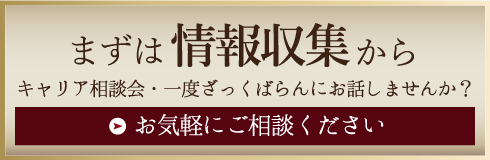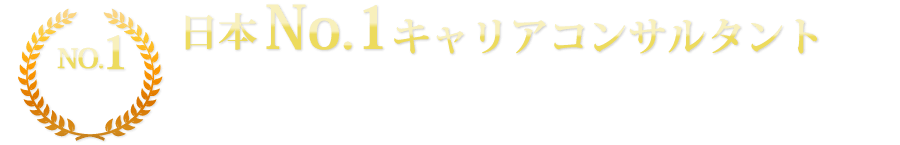簿記2級の合格率は何%?
簿記2級とは?試験概要と出題範囲
日商簿記2級は、日本商工会議所が主催する簿記検定の中級レベルに位置づけられており、主に企業の経理実務や財務分析の基礎を身につけるための資格です。
特に商業高校・大学の経済学部・商学部の学生や、経理・事務職を目指す社会人に人気があります。
試験方式(2025年現在):
統一試験(ペーパー式):年3回(2月・6月・11月)
ネット試験(CBT方式):全国の試験会場で随時受験可能(予約制)
合格基準:
100点満点中70点以上で合格(部分点あり)
配点は毎回異なるが、商業簿記と工業簿記を合わせて出題される
どんな人が受験しているのか
簿記2級の受験者は、主に以下のような層が中心です。
商業高校・大学生:就職活動に有利な資格として取得
社会人(経理職・FAS):スキルアップ・転職・昇進のため
主婦・転職希望者:事務職へのキャリアチェンジに備えて
資格マニア:他の資格(FP・税理士・公認会計士)の前段階として
最近では、リスキリング(学び直し)や副業支援制度の一環として、企業が社員に受験を奨励しているケースも増えています。
簿記2級の合格率の推移(最新?過去10年)
2025年第1回試験の合格率
2025年6月に実施された第167回 日商簿記2級(統一試験)の合格率は、16.8% でした(※日本商工会議所発表データより)。
| 試験回 | 試験日 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|
| 第167回 | 2025年6月 | 16.8% | 約25,000人 | 約4,200人 |
この合格率は、例年よりやや低めの傾向です。試験問題が応用的だったことや、特定の論点(例:本支店会計、直接原価計算など)の出題比重が高かったことが要因と考えられます。
過去10年の合格率の平均と変動傾向
日商簿記2級の合格率は、過去10年間で平均20?30%台と大きく変動しています。
特に難化傾向が顕著だったのは2016年?2019年ごろで、10%台前半という厳しい年もありました。
| 年度 | 回数 | 合格率 |
|---|
| 2025 | 第167回 | 16.8% |
| 2024 | 第166回 | 21.3% |
| 2024 | 第165回 | 27.5% |
| 2023 | 第164回 | 18.2% |
| 2022 | 第160回?163回 | 平均25%前後 |
| 2021 | 第157回?159回 | 15?28% |
| 2020 | 第155回?156回 | 約28%前後 |
| 2019 | 第153回 | 13.4% |
| 2018 | 第150回?152回 | 平均15?20%前後 |
| 2015?2017 | - | 平均25?30%前後 |
難易度のばらつきが激しいため、合格率の数字だけでは判断しきれない
回によっては「簿記1級より難しい」との声もあるほど
受験者数の推移
かつては毎年50万人近くが受験していた日商簿記検定ですが、近年は減少傾向にあります。
| 年度 | 2級受験者数(統一試験) |
|---|
| 2010年 | 約45万人 |
| 2020年 | 約25万人 |
| 2024年 | 約18万人 |
| 2025年(予測) | 約15万人前後 |
背景としては、ネット試験導入により受験機会が分散されたこと、簿記3級止まりで満足する人が増加、他の資格(FP・MOSなど)との比較検討が進んでいることが挙げられます。
簿記2級の難易度は?合格率から見る本当の難しさ
なぜ合格率が低い?よくある失敗ポイント
簿記2級は、3級と比べて一気に難易度が上がる資格です。合格率が20%前後にとどまっている理由は、出題内容の難しさだけでなく、受験者の「準備不足」も影響しています。
| 失敗例 | 原因・背景 |
|---|
| 基礎があいまいなまま応用問題に進む | 仕訳や精算表の理解が不十分 |
| 工業簿記を軽視する | 商業簿記に比べて出題ボリュームが少ないため後回しにされがち |
| 過去問ばかり解いて新傾向に対応できない | 近年は“思考型”の新しい出題が増加 |
| 勉強時間が足りない | 最低でも150?250時間は必要とされるが、実際は半分以下で受験する人も多い |
3級との違い・ギャップが難易度の原因?
| 項目 | 3級 | 2級 |
|---|
| 学習範囲 | 基本的な商業簿記 | 商業簿記+工業簿記(企業会計の原則) |
| 問題傾向 | 定型的な問題が中心 | 思考力・応用力を問う出題が多い |
| 試験形式 | 選択肢が多く計算も少なめ | 総合問題・記述問題・仕訳も複雑 |
| 勉強時間目安 | 50?80時間 | 150?250時間以上 |
特に、工業簿記は「はじめて見る概念」も多く、数学的な考え方(公式や原価計算)に苦手意識を持つ受験者も少なくありません。
「3級に合格している=2級に通用する」わけではないので、完全にゼロから学ぶ気持ちで取り組むことが合格への近道です。
合格率を上げるための勉強法と対策
おすすめの勉強時間とスケジュール
日商簿記2級に合格するためには、最低でも150?250時間の学習が必要と言われています。社会人や学生のライフスタイルに合わせた学習計画を立てることが、合格へのカギです。
| 期間 | 内容 | 学習時間の目安 |
|---|
| 1ヶ月目 | 商業簿記の基礎・仕訳・勘定科目の理解 | 約50?60時間 |
| 2ヶ月目 | 工業簿記・精算表・伝票・仕訳帳の練習 | 約50?60時間 |
| 3ヶ月目 | 過去問演習・総合問題・模擬試験対策 | 約50?80時間 |
ポイント
・最初の1か月で「理解」に重点を置く
・2か月目からは「アウトプット重視」へ切り替え
・直前期は過去問と模試を徹底的に繰り返す
使うべき参考書・通信講座
独学か通信講座かによって選ぶ教材は変わります。ここでは人気の高い教材・講座を紹介します。
独学派におすすめの参考書・問題集
| 書籍名 | 特徴 |
|---|
| スッキリわかる日商簿記2級(TAC出版) | 初心者向けの定番。図解が豊富でやさしい |
| よくわかる簿記シリーズ(ネットスクール) | 詳細な解説で理解を深めたい人向け |
| 合格テキスト+合格トレーニング(日商簿記2級・TAC) | 応用問題も多く、演習量を確保できる |
通信講座の人気ランキング(2025年版)
| 講座名 | 特徴 | 価格帯 |
|---|
| ユーキャン | 初学者向け、サポート体制が手厚い | 約49,000円? |
| スタディング | スマホ完結、スキマ時間を活かせる | 約24,800円? |
| クレアール | 合格特化型カリキュラム、再受講無料制度あり | 約30,000円? |
| フォーサイト | フルカラー教材+eラーニングが充実 | 約45,000円? |
よく出る論点と頻出問題パターン
近年の試験傾向から、以下のテーマが頻出分野となっています。
商業簿記の頻出論点
| 本支店会計(支店独立会計・内部取引) |
| 有価証券・固定資産の処理 |
| 精算表と試算表 |
| 伝票会計・仕訳帳 |
工業簿記の頻出論点
| 製造間接費の配賦計算 |
| 個別原価計算と総合原価計算の違い |
| CVP分析(損益分岐点・限界利益) |
試験でのポイント
・仕訳ミス=0点のリスクあり → ミス防止の訓練必須
・最新の試験では「思考力」を問う非定型問題が増加傾向
重要なのは、満遍なくやるより「頻出テーマを徹底的にやり込む」ことです。
模試や過去問を通じて、時間配分や記述のクセも慣れておくと安心です。
まとめ|合格率に惑わされず、正しい対策を
日商簿記2級は、合格率だけを見れば「難しい資格」と感じるかもしれません。実際に合格率は年によって10?30%と大きく変動し、3級とのギャップに戸惑う受験者も少なくありません。
しかし、合格率の低さ=合格できない試験では決してありません。
合格に必要なのは「正しい戦略と継続」
・頻出論点に絞って学習する
・学習時間を確保し、3か月?6か月の計画を立てる
・過去問や模擬試験で「本番力」を養う
・独学が難しい場合は通信講座を活用する
こうした「王道の対策」をしっかり行えば、社会人でも学生でも十分合格は狙えます。
合格率に振り回されず、冷静な準備を
試験ごとの合格率はあくまで“参考情報”であり、一人ひとりの努力次第で結果は変えられます。
「今回の合格率は低かった」と思っても、それが自分に当てはまるとは限りません。
「受かる人は受かっている」それが簿記2級の現実です。
転職を検討中という方は、弊社ムービンまでお気軽にご相談ください!


 初めての方へ - 転職を検討される金融業界の方へ【キャリアの考え方】
初めての方へ - 転職を検討される金融業界の方へ【キャリアの考え方】