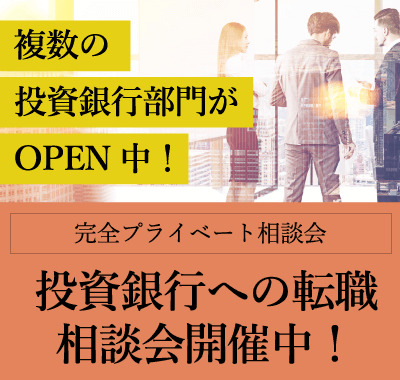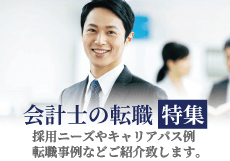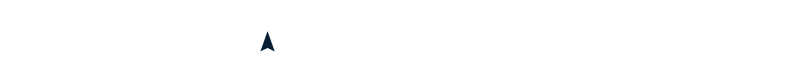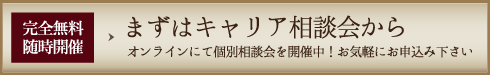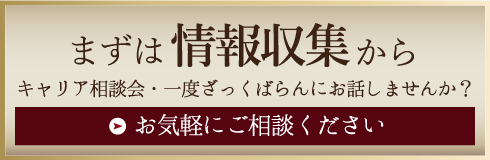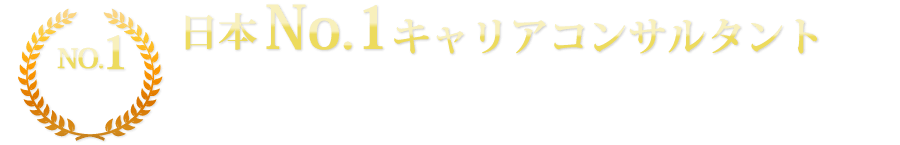- 金融転職サイトTOP >
- 金融業界の転職 特集 >
- 監査とは?意味から種類・目的・実施プロセス・必要性までわかりやすく解説【初心者向け】
監査とは?意味から種類・目的・実施プロセス・必要性までわかりやすく解説【初心者向け】

「監査」は、企業の財務情報や業務プロセス、コンプライアンスを独立した立場から検証し、信頼性と透明性を担保する仕組みです。
とりわけ会計監査は、財務諸表が基準と法令に適合しているかを確認し、投資家や取引先の意思決定を支えます。
本記事では、内部監査と外部監査の違い、会計監査の目的と流れ、監査法人・公認会計士の役割、検査・調査・評価との違いを整理。
さらに、AI・DXによる次世代監査の動向、実務で用いられる手法やツール、学習の始め方までを網羅的に解説します。
監査の全体像を掴み、キャリアや実務にどう生かせるかを具体的にイメージできる内容です。
年収アップをしたい方は、弊社ムービンまでお気軽にご相談ください!
監査とは?まずは一言で説明すると
「監査」とは、企業や組織の財務状況、業務プロセス、コンプライアンスなどを独立した第三者が検証・評価する活動のことです。
ビジネスの場面では特に、企業の会計情報が正確であるかどうかをチェックする「会計監査」が広く知られています。
監査の目的は、企業の財務報告が正確で信頼性があるかを確認し、不正や誤りがないかをチェックすることです。
会社が発表する財務諸表(決算書)が正しい内容であるかをチェックし、投資家・取引先・金融機関などの利害関係者が安心してその情報を使えるようにするために行われます。
監査は「内部監査」と「外部監査」に大きく分けられ、それぞれ役割や目的が異なります。
さらに、会計だけでなく、業務全般やシステム、コンプライアンスなど、対象となる範囲も多岐にわたります。
なぜ監査が必要なのか?
監査が必要な理由は、企業や組織が適正に運営され、ステークホルダー(株主、投資家、顧客、従業員など)の信頼を得るために不可欠だからです。具体的な理由は以下の通りです:
1. 信頼性の確保
監査によって、企業の財務諸表が正確で信頼できるものであることが確認されます。
投資家や取引先は、企業の経済的な健全性を判断するために、信頼性の高い情報を求めています。
監査を通じて、企業の財務報告が誤りや不正なく透明であることが証明されます。
2. 不正防止とリスク管理
監査は、企業内での不正行為(例えば、財務報告の改ざんや資金の不正流用など)を発見し、予防するための重要な手段です。
監査の過程で、不正の兆候やリスクが早期に明らかになり、これを防止するための対策が取られることがあります。
3. 法的および規制の遵守
企業は法律や業界の規制に従わなければならないため、監査はその遵守状況を確認します。
法的要件に適合していない場合、罰則や信頼喪失のリスクがあります。
監査によって、これらのコンプライアンス違反が早期に発見され、適切に対応することができます。
4. 経営の透明性の向上
監査を受けることで、経営活動の透明性が高まります。
企業の経営陣が意図的に隠蔽しようとしている情報を公開するため、ステークホルダーに対して誠実さを示すことができます。
5. 資金調達の円滑化
企業が資金調達を行う際、投資家や銀行はその企業の財務状況を慎重に評価します。
監査を受けた財務諸表は、外部の専門家によって検証されたものであり、信頼性が高いため、資金調達が円滑に進む可能性が高くなります。
6. 経営改善のためのフィードバック
監査は、単に問題を指摘するだけでなく、業務プロセスや内部管理の改善点についてもアドバイスを提供することがあります。
これにより、経営の効率化や改善に繋がります。
7. 企業の評価向上
監査を受けた企業は、外部からのチェックを受けて透明性が高いと見なされるため、取引先や顧客、投資家からの信頼を得やすくなります。
また、企業評価やブランド価値が向上することにもつながります。
監査の種類|外部監査と内部監査の違い
監査には「外部監査」と「内部監査」の2種類があります。
それぞれの特徴と役割を正しく理解することで、監査の全体像が見えてきます。
1. 監査を行う主体
外部監査
外部監査は、独立した第三者(例えば、公認会計士や外部監査法人)によって実施されます。
これにより、監査の結果が客観的で中立的であることが保証されます。
内部監査
内部監査は、企業内の専任部門やスタッフ(内部監査部門)によって実施されます。
内部監査人は企業の社員であり、業務の改善やリスク管理に焦点を当てることが多いです。
2. 目的
外部監査
外部監査の主な目的は、企業の財務諸表が正確で信頼性があり、会計基準や法律に従って作成されているかどうかを検証することです。
また、ステークホルダー(株主や投資家)に対して、企業が正しい財務情報を提供していることを証明する役割を果たします。
内部監査
内部監査の目的は、企業内部の業務やプロセスが効率的に運営され、リスク管理や内部統制が適切に行われているかを確認することです。
経営陣に対して改善点やリスクを指摘し、業務の最適化をサポートします。
3. 対象範囲
外部監査
外部監査は主に企業の財務諸表や会計記録に焦点を当てます。
企業全体の財務状況を評価し、その正確性を証明するために行われます。
内部監査
内部監査は、財務報告に限らず、企業の業務全般(業務プロセス、内部統制、コンプライアンス、リスク管理など)を監査対象とします。
業務効率や内部の安全管理、法令遵守状況なども確認します。
4. 報告先
外部監査
外部監査の結果は、企業の経営陣、株主、投資家、金融機関など、外部のステークホルダーに対して報告されます。
外部監査の結果は、企業の信頼性や透明性に大きく影響を与えます。
内部監査
内部監査は、主に経営陣(CEOや取締役会など)に報告され、改善のための提案を行います。
企業内部での問題点やリスクを報告し、組織の運営改善を目的とします。
5. 監査の頻度
外部監査
外部監査は、通常、年に一度行われます。
主に年度ごとの財務報告を対象に行われるため、定期的な監査になります。
内部監査
内部監査は、企業のニーズに応じて、頻繁に実施されることがあります。
通常、年間を通じて継続的に行われ、必要に応じてその範囲や内容が調整されます。
年収アップをしたい方は、弊社ムービンまでお気軽にご相談ください!
会計監査とは?財務諸表をチェックする目的と流れ
会計監査とは、企業が作成した財務諸表(決算書など)が、会計基準や法令に従って正しく記載されているかどうかを、第三者である公認会計士や監査法人がチェックするプロセスです。
特に上場企業などでは、金融商品取引法や会社法に基づき、監査の実施が義務づけられています。
この監査は、企業が財務報告において正確な情報を提供し、法的および会計基準に従っているかを確認することを目的としています。
投資家や金融機関、取引先などの利害関係者は、企業の数字をもとに意思決定を行うため、その情報が間違っていては大きな損失につながる可能性があるからです。
会計監査は次のようなプロセスで行われます:
計画と準備
監査人は、監査計画を策定し、企業の業務や内部統制の仕組みを理解します。
監査計画には、監査対象の財務諸表や関連するリスクの特定が含まれます。
実施
監査人は、企業の財務諸表の項目に対して詳細な検証を行います。
これには、取引記録や証拠書類の確認、内部統制の評価、サンプリングによる取引の検証などが含まれます。
監査結果の評価
監査人は、検証の結果を評価し、財務諸表が会計基準に適合しているか、不正や誤りがないかを確認します。
監査報告書の作成
最終的に、監査人は監査報告書を作成します。
報告書には、財務諸表が「適正である」とする意見や、「適正でない」とする意見、または「意見を表明しない」とする場合などが記載されます。
監査法人と公認会計士の役割
監査を実施する中心的な存在が、公認会計士と監査法人です。
これらの専門家は、財務や会計、法令に関する高度な知識と実務能力を有し、企業の情報を客観的かつ公正に評価する役割を担っています。
公認会計士は、国家資格に合格した会計の専門家で、会計監査を行うための法的権限を持っています。
彼らは企業の財務諸表をチェックするだけでなく、税務や経営アドバイス、コンサルティングなどの分野でも幅広く活躍しています。
一方で、上場企業などの規模の大きな企業では、監査を1人の会計士で行うことは現実的ではありません。
そのため、複数の公認会計士が共同で設立した「監査法人」が、チーム体制で監査を行います。
日本には「Big4(ビッグフォー)」と呼ばれる大手監査法人(トーマツ、あずさ、あらた、PwC)があり、国内外の大企業を中心に多数の監査を担当しています。
監査法人の業務は、高い専門性と厳格な独立性が求められ、企業からの信頼を得るために厳格な基準のもとで運営されています。
そのため、監査報告書が出されるということは、第三者の専門機関によって財務内容が「適正」と判断されたことを意味するのです。
監査と検査・調査・評価との違い
「監査」と似たような言葉に、「検査」「調査」「評価」などがありますが、それぞれ目的や実施主体、手法が異なります。
監査は、法令や基準に基づいて、企業や組織の情報や業務が適正に行われているかを第三者の視点で体系的に検証する行為です。
一方、検査はより技術的で形式的なチェック、調査は事実確認や実態把握、評価は定性的・定量的にパフォーマンスを判断することに重点があります。
監査は結果に対して責任が問われる性質も強く、信頼性の高いアウトプット(監査報告書など)を生み出すことが求められるという点でも、他の概念とは一線を画しています。
監査の将来性とAI・DXとの関係
監査の世界でも、近年は急速にAI(人工知能)やDX(デジタルトランスフォーメーション)の波が押し寄せています。
これまで監査業務といえば、大量の書類を目視で確認したり、手作業でデータ分析を行うことが主流でした。
しかし、現在は、会計ソフトやクラウドサービスとの連携により、取引データの自動抽出や不正検知、異常値の分析などが可能になりつつあります。
AIの活用により、高精度かつスピーディーな監査が可能になる一方で、監査人にはこれまで以上に「リスクを見抜く目」や「判断力」「倫理観」が求められるようになってきました。
また、監査法人でもRPA(業務自動化)やビッグデータ分析を導入するなど、テクノロジーを駆使した次世代監査が進行中です。
これからの監査は、単なる「チェック業務」ではなく、企業価値や経営戦略に貢献する専門的活動へと変わっていくことが予想されます。
監査に興味を持ったら、まず何から始める?
監査という分野に関心を持ったら、最初の一歩は「基本的な会計知識を身につけること」です。
なぜなら、監査の多くは会計情報を前提として成り立っているからです。
まずは日商簿記3級や2級レベルの学習から始めてみるのがおすすめです。
簿記を学ぶことで、企業の収益構造や会計処理の仕組みが理解できるようになり、監査に必要な基礎知識が身につきます。
次に、監査の実務や制度について書かれた入門書を読む、あるいはYouTubeや講座動画などで概要をつかむことで、全体像を把握できます。
さらに本格的に監査業務に関わりたい場合は、公認会計士試験について調べることが次のステップになります。
試験科目や合格までの道のり、資格取得後のキャリアパスなどを理解することで、自分に合っているかどうかを判断できるようになります。
また、学生や未経験者でも、監査法人のインターンシップやアルバイトで実務を体験することも可能です。
現場の雰囲気を感じながら、具体的に自分の適性や興味を見極めることができる貴重な機会になります。
監査は知識だけでなく、論理的な思考力や倫理観も求められる分野です。
そのため、単に試験に合格するだけでなく、社会的責任を意識しながら成長していく意欲が重要とされます。
監査の実務で使われるツールや手法
監査業務は、「資料を確認して問題があるかを探す」だけの単純作業ではありません。
膨大な情報の中からリスクを見つけ出し、限られた時間で効率よく信頼性を検証するために、監査人はさまざまなツールや手法を使い分けながら実務を進めています。
監査調書(ワーキングペーパー)
監査の基本となるのが「監査調書(ワーキングペーパー)」です。
これは、どのような手続を実施し、どのような証拠を得て、どんな判断を下したのかを記録したものです。
調書は、後から監査の正当性を説明する根拠にもなるため、詳細かつ客観的に記録されることが求められます。
現代では紙ではなく、専用のシステム上で電子化された調書を作成するのが一般的です。
リスクアプローチ(リスクベース監査)
すべての取引や資料を均等にチェックするのは非現実的であるため、実務では「リスクアプローチ」という考え方が導入されています。
これは、財務諸表に重大な影響を与える可能性のある領域(リスクが高い分野)に重点を置いて監査を行う手法です。
たとえば、売上が急増している部署や、在庫評価に大きな見積もりが関与している勘定科目などは、リスクが高いと判断され、重点的に監査されることになります。
分析的手続
分析的手続とは、前年との比較、業界平均との比較、トレンド分析などを通じて、異常な変動や不整合を見つけ出す方法です。
これにより、問題のある領域を特定しやすくなり、効率的な監査が可能となります。
例えば、売上は増加しているのに売掛金が減っているといった不自然な変化があれば、その背景に何かしらのリスクや誤りが潜んでいるかもしれません。
実査・立会・外部確認
財務諸表に記載された数値が実態と一致しているかを確認するため、監査人は実地での調査や第三者への確認も行います。
実査:在庫や現金など、実際に物理的に存在するかを確認する作業
立会:棚卸しや現金確認の場に同席し、不正がないかを見届ける
外部確認(確認状):取引先や銀行などに対し、残高や取引内容について直接確認する手続き
これらは「監査証拠」を集めるための重要な手法であり、信頼性の高い情報源として重視されています。
ITツール・監査ソフトウェア
近年では、監査専用のソフトウェアやクラウドツールの導入が進んでいます。
たとえば、EY Canvas や Deloitte Connect などのグローバルな監査プラットフォームでは、進捗管理・調書作成・証憑管理などが一元化され、ペーパーレスかつリアルタイムの監査が実現されています。
また、ExcelやPower BIなどを使ったデータ分析、AIによる異常検出、RPAによる定型作業の自動化なども実務に取り入れられており、監査業務はますます高度化・効率化が進んでいます。
このように、監査の現場では数多くの専門的な手法とツールが活用されており、単なる帳簿の確認ではなく、企業の経営実態に踏み込んだ高度な検証活動が行われているのです。
今後、テクノロジーの進化とともに、監査人の役割はますます戦略的なものへと変化していくことが予想されます。
まとめ|監査は企業の信頼を守るための重要な機能
監査とは、企業の財務情報や業務プロセスが正しく行われているかを、第三者が客観的に確認・評価する行為です。
とくに上場企業や大企業では、会計監査が法律で義務づけられており、投資家・取引先・社会全体からの信頼を支える基盤となっています。
監査には「外部監査」と「内部監査」があり、それぞれ目的や役割が異なりますが、共通するのは透明性のある経営を実現するためのチェック機能であるという点です。
近年は、AIやクラウド技術の進化によって、監査業務もデジタル化が進み、ますます戦略的で高度なスキルが求められるようになってきました。
単なる「確認作業」ではなく、企業活動の本質に関わる専門性の高い知的業務へと発展しています。
もし監査という分野に興味を持ったなら、まずは会計の基礎を学び、徐々に監査制度や実務に触れていくのがおすすめです。
公認会計士や内部監査士といった専門資格を目指すことで、社会的信頼性の高いキャリアを築くことも可能です。
監査は目立たない仕事かもしれませんが、企業活動の健全性を守る、極めて重要な役割を果たしています。
その本質を理解し、自らのキャリアにどう関わっていくか、ぜひじっくり考えてみてください。
年収アップをしたい方は、弊社ムービンまでお気軽にご相談ください!
- トップ営業マンの転職-さらなる可能性を広げるためのキャリアパス-
- フィンテック(Fintech)業界特集
- 事業再生・企業再生ポジションの最新動向
- 常駐支援型アドバイザリーポジション特集
- 4大監査法人への転職 特集
- 保険営業職からの転職 特集
- 金融・アドバイザリーにおける海外勤務ポジション特集
- 金融業界から監査法人への転職事例
- 金融第二新卒からのコンサル、事業会社への転職
- 【最新版】証券会社出身者のキャリアプランを考える(すぐに使える転職情報)
- 保険業界への転職・最新事情
- 国際開発・海外インフラ関連ポジション
- 分かっているようで知らない?銀行業界の全体像
- 海外進出支援コンサルティング・アドバイザリーへの転職
- 官民連携ポジション 最新採用動向
- 保険業界からのコンサル転職特集
- 金融業界・FAS業界からベンチャー企業への転職
- 【特集】アセットマネジメント業界への転職
- 【年収UPの方法】税理士・税理士試験科目合格者向け 転職特集
- 【注目分野!】監査法人アドバイザリー部門への転職 特集
- 税理士、税理士試験科目合格者の転職【成功事例】 特集
- 独立系財務アドバイザイリーファーム 特集
- 金融業界からコンサルティング業界への転職
- 外資系証券会社への転職事情
- 特集 銀行・証券リテールからのM&A・財務アドバイザリー転職【成功事例】
- 特集 不動産金融・アドバイザリーポジションの最新転職動向
- 監査法人出身者のキャリアアップ転職【成功事例】
- 【証券リテール営業の転職先】積極的に求める業界・企業をご紹介! -
- 特集 人材紹介会社を使うメリットとは
- 特集 日本を支える中堅中小企業を支援するポジション
- 注目を浴びる株式市場 〜株価が動くメカニズム〜
- 転職活動におけるマナー
- 特集 転職活動に役立つ参考書籍 第3弾(筆記&Web試験対策)
- 積極採用!シンクタンクのコンサルティングポジション特集
- 転職活動に役立つ参考書籍
- 事業会社財務ポジションへの転職特集
- バイサイドへの転職・最新事情
- 金融業界での第二新卒転職 転職活動における志望動機書の書き方
- 金融業界での第二新卒転職 初めての転職活動〜傾向と対策〜
- PEファンドからの転職考察
- ニーズが高まる生命保険業界への転職
- 第2新卒・若手層の金融業界転職
- 【特集】ハンズオン支援コンサルティングファームへの転職
- 難関職種・アクチュアリーの転職事情
- 金融業界におけるITポジションの採用動向
- ポスト金融転職 〜金融業界からの転職〜 特集
- 今後注目の生命保険業界 特集
- 日本企業の海外進出支援 特集
- 不動産ファイナンスポジションの転職市場 特集
- 金融機関出身者の転職事情 特集
- 国際会計基準(IFRS)関連業務 特集
- 銀行・ファイナンス業務 特集
- 金融業界アナリストの転職事情
- 【特集】移転価格コンサルタント転職(Transfer pricing Taxation)
- 企業再生ビジネスにおけるコンサルティングファーム採用動向特集
- ムービンキャリアコンサルタントが語る「ファンド業界」最新採用動向
 初めての方へ - 転職を検討される金融業界の方へ【キャリアの考え方】
初めての方へ - 転職を検討される金融業界の方へ【キャリアの考え方】
各出身業界・バックグラウンド・ご志向別に、どのようなキャリア選択肢があるのか、採用動向や実際にご支援させて頂いた転職事例などをご紹介いたします。