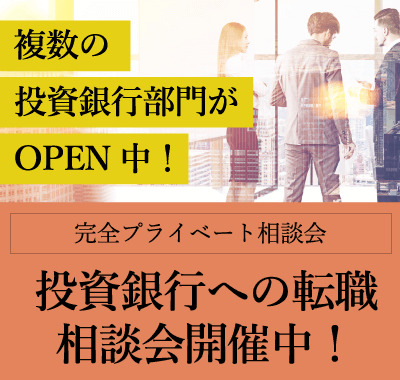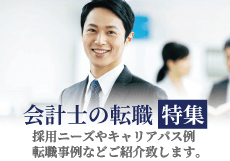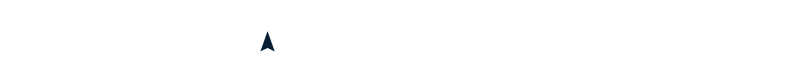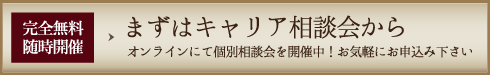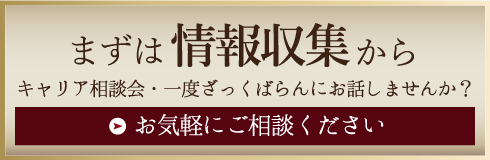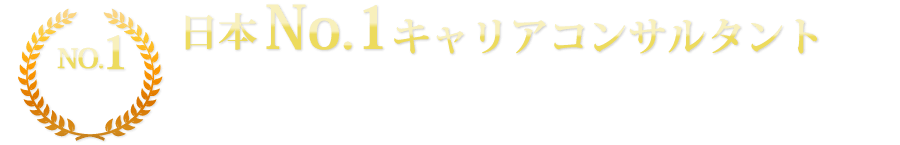会計士と税理士の違いを徹底解説|業務・資格・依頼先の選び方までわかりやすく解説

会計士とは? - 業務内容と特徴
公認会計士(CPA)とは、企業の財務諸表が正しく作成されているかを第三者の立場でチェックする「監査業務」を中心に、会計や財務のプロフェッショナルとして活動する国家資格者です。
特に上場企業や大手企業においては、法的に監査を受ける義務があるため、公認会計士の役割は非常に重要です。
公認会計士の主な業務内容
| 業務 | 内容 |
| 監査業務 | 上場企業や大企業の財務諸表が会計基準に従って正しく作成されているかをチェック(独占業務) |
| コンサルティング業務 | M&Aや事業再生、経営戦略立案など、企業の経営判断に関わる助言 |
| 財務アドバイザリー | 資金調達や内部統制の支援など |
| 税務業務(※税理士登録後) | 税務申告・節税対策なども可能になる(税理士登録が前提) |
公認会計士の特徴と強み
監査業務は会計士のみが行える独占業務
税理士や他の専門家が行えない「財務諸表監査」は、公認会計士のみに許された業務です。企業の透明性や信頼性を担保する役割として社会的責任も重く、高い倫理観と専門知識が求められます。
クライアントの多くは上場企業や大手企業
公認会計士は、一般的に「監査法人」と呼ばれる大規模な事務所に所属し、上場企業を対象に業務を行うケースが多いです。安定した職業としても人気が高く、専門性を活かしてコンサルタントやCFO(最高財務責任者)に転身する人もいます。
独立開業も可能だが、税理士登録が必要な業務もある
公認会計士は税理士登録を行うことで、税務申告や節税アドバイスなどの税務業務も対応可能になります。実際、税理士登録を行って独立し、中小企業を中心にサポートする公認会計士も多数存在します。
難関資格でありながら将来性は高い
試験合格率は10%前後と難易度は高いですが、経済のグローバル化や企業のコンプライアンス強化により、今後も需要は高まると予想されています。また会計士は転職においても有利な資格とされています。
税理士とは? - 業務内容と特徴
税理士とは、個人や法人の税務に関する専門家であり、税金の申告や相談、税務代理業務を行う国家資格者です。主に中小企業や個人事業主の顧問として、日々の経理から節税対策まで幅広くサポートします。
公認会計士の主な業務内容
| 業務 | 内容 |
| 税務代理 | 所得税や法人税などの申告書作成と提出を代行 |
| 税務書類の作成 | 確定申告書・相続税申告書・各種届出書などの作成 |
| 税務相談 | 節税・税法の解釈・相続対策などのアドバイス |
| 会計業務 | 記帳代行、決算書作成、会計ソフトの導入支援など |
税理士の特徴と役割
税に関する業務のスペシャリスト
税務申告や節税、相続税対策など、「お金」にまつわる実務に強く、一般の人や中小企業経営者の最も身近なパートナーとなります。
業務範囲が幅広く、日常的な経理支援も対応
記帳代行や会計ソフトの導入、毎月の月次処理など、日常的な経理業務を担うケースも多く、「数字が苦手な経営者」の強い味方です。
個人事業主や中小企業との関わりが深い
法人税や所得税、消費税などの申告業務を通じて、起業初期から長く付き合う顧問税理士として活躍するケースが一般的です。
相続・贈与など個人の相談も多い
高齢化社会に伴い、相続や贈与に関する相談が増えており、個人のライフプランに関わる分野でも重要な役割を果たしています。
税理士になるには複数のルートがある
国家試験に合格する他にも、公認会計士や弁護士資格を持っている場合、自動的に税理士登録が可能です。
公認会計士と税理士の重複業務もある
実は、税理士の業務の一部は公認会計士でも税理士登録すれば対応可能です。実際に、会計士資格を持ちつつ税理士登録をしている専門家も多く存在し、ワンストップで監査・税務の両方を請け負うケースも見られます。
会計士と税理士の比較表
公認会計士と税理士は、どちらも「お金の専門家」という共通点がありますが、業務の範囲や対象、資格の取得方法などに明確な違いがあります。
ここでは、両者の違いを一覧表でわかりやすく比較します。
| 比較項目 | 公認会計士 | 税理士 |
| 主な業務 | 財務諸表監査、会計アドバイザリー、コンサルティング | 税務申告、税務相談、記帳代行、相続税対策 |
| 独占業務 | 監査業務(例:上場企業の財務諸表監査) | 税務代理・税務書類の作成・税務相談(いずれも独占) |
| 主なクライアント | 上場企業、大企業、監査法人経由の法人クライアント | 中小企業、個人事業主、相続や贈与の相談者 |
| 資格取得方法 | 公認会計士試験合格+実務経験2年以上+修了考査合格 | 税理士試験合格、または会計士・弁護士から登録 |
| 試験難易度 | 非常に高い(合格率約10%前後) | 難易度は高いが科目合格制度があり段階的に取得可能 |
| 税務業務の可否 | 税理士登録をすれば可能 | 監査業務は不可 |
| 年収の目安(平均) | 約800万円〜1,000万円以上(※監査法人勤務時) | 約600万円〜800万円(※開業や規模により差が大きい) |
| 将来性 | 会計・監査のニーズ増で高い | 相続・中小企業支援ニーズは安定的にあり |
資格取得の難易度と勉強方法の違い
公認会計士と税理士はどちらも国家資格ですが、試験制度や勉強期間、難易度には大きな違いがあります。
ここでは、それぞれの資格取得までのプロセスと難易度を比較して解説します。
公認会計士の資格取得の流れ
公認会計士は、日本三大難関国家資格の一つとされ、短期間での合格は非常に難しいといわれています。
公認会計士試験の流れ
短答式試験(年2回)
→ 財務会計論、管理会計論、監査論、企業法の4科目
論文式試験(年1回)
→ 会計学、監査論、租税法、経営学・民法・統計学(選択)
合格後は、2年以上の実務経験と、修了考査という最終試験に合格して初めて「公認会計士」として登録できます。
? 合格率と勉強期間の目安
合格率:10?11%前後(論文式まで含めたトータル)
必要な勉強期間:2?3年(1日8時間以上の勉強が必要なことも)
対象者:大学在学中から専門学校等に通い勉強する人が多い
税理士の資格取得の流れ
税理士試験は、全11科目の中から5科目を合格すればOKという「科目合格制度」が特徴です。
税理士試験の構成
【必須】簿記論・財務諸表論(2科目)
【選択】法人税法・所得税法など(残り3科目を選択)
1科目ずつ合格すれば有効期限なく持ち越せるため、働きながら取得する社会人も多くいます。
? 合格率と勉強期間の目安
科目ごとの合格率:10?20%程度(科目により差あり)
5科目合格まで:平均5?7年かかる人が多い
対象者:社会人や経理職からのキャリアアップ目的の人が多数
| 比較項目 | 公認会計士 | 税理士 |
| 試験制度 | 一発合格型(短答+論文+修了考査) | 科目合格制(5科目合格でOK) |
| 勉強期間の目安 | 2?3年(専念が前提) | 5?7年(働きながらでも可能) |
| 合格率(全体) | 約10%前後 | 科目別10?20%、全体での達成は数% |
| 主な学習方法 | 専門学校・大学+予備校 | 働きながら専門学校、通信講座など |
会計士・税理士のキャリアパスと転職先
公認会計士や税理士は、資格を取得したあとも多様なキャリアパスが用意されており、特に近年は「独立開業」だけでなく、「一般企業への転職」「コンサルティング業界への進出」「スタートアップ支援」など、選択肢が大きく広がっています。
以下、それぞれのキャリアについて詳しく解説します。
公認会計士の主なキャリアパス
| キャリア先 | 特徴・内容 |
| 監査法人(BIG4含む) | 新卒〜若手会計士の多くが就職。財務諸表監査・内部統制評価などが中心。 |
| 一般事業会社(経理・財務部門) | 上場企業や大手企業に転職し、経理・CFO候補として活躍。 |
| コンサルティング会社(FAS/戦略系) | M&A、事業再生、デューデリジェンス業務などで需要が高まっている。 |
| 独立開業 | 監査・税務・会計コンサルをワンストップで提供。個人や中小企業支援も。 |
| スタートアップ支援 | CFOや会計顧問としてスタートアップの経営支援に携わる人も増加中。 |
特に近年は「会計×IT」「会計×M&A」といった複合スキルが重宝されており、データ分析・経営企画など、非会計分野への進出も増えています。英語力やグローバル案件対応経験があると、外資系企業でのキャリアも視野に入ります。
税理士の主なキャリアパス
| キャリア先 | 特徴・内容 |
| 税理士法人・会計事務所 | 最も一般的なキャリア。顧問先の税務申告・経営支援など。 |
| 一般企業(経理・財務・経営企画) | インハウス税理士として、社内の税務処理や節税戦略を担う。 |
| 相続・資産税専門事務所 | 富裕層向けの資産管理、相続・贈与対策のスペシャリストとして活躍。 |
| 独立開業 | 自分の顧問先を持ち、自由な働き方を実現。地方でのニーズも高い。 |
| コンサルティング・金融業界 | 税務知識を活かしてM&A・事業承継・財務コンサル業務に転身可能。 |
公認会計士と税理士では、キャリア形成の傾向や活躍の場に違いがあります。
まず公認会計士は、多くの場合、キャリアのスタート地点として監査法人(BIG4など)に就職します。ここで財務諸表監査や内部統制の評価などを経験し、キャリアを積んでいきます。その後は、上場企業の経理・財務部門や、コンサルティング会社・金融機関などへの転職も多く見られます。特にM&Aや企業再生といったハイレベルな業務に関わるケースが増えており、年収も600万円?1,500万円以上と幅広く、ポジションによっては非常に高収入を得ることも可能です。
独立開業ももちろん可能ですが、法人監査を扱うには一定の実務経験や営業力が求められるため、企業内での経験を積んだ後に独立する人も多いです。
一方で税理士の場合、初期キャリアとして選ばれるのは、税理士法人や中小規模の会計事務所です。税務申告や記帳代行、顧問先とのやり取りを通じて実務経験を積み、その後、相続特化の事務所に転職したり、一般企業の税務部門(インハウス税理士)として働いたりする人もいます。年収は500万?1,200万円ほどで、独立後は顧問契約を積み上げて安定的に収入を得るケースが多いです。比較的開業のハードルが低く、地方でもニーズが安定しているため、自営業として成功する人も少なくありません。
全体として、公認会計士は「大企業・グローバル案件に強い専門職」という側面が強く、税理士は「中小企業や個人の経営・税務を支える身近なパートナー」としての色合いが濃いキャリアです。どちらも将来性はありますが、目指すライフスタイルや働き方に応じて、どちらが自分に合っているかを考えることが重要です。
女性のキャリア視点|資格を活かした柔軟な働き方が可能
公認会計士・税理士の資格は、結婚や出産などライフイベントを迎えたあともキャリアを継続しやすいという点で、女性にも非常に適した職業です。
特に税理士は、働く場所や時間を比較的柔軟に調整できることから、育児と両立しながら在宅で記帳や申告業務を請け負うフリーランス女性も増えています。
一方、公認会計士は監査法人に勤務している間は繁忙期の残業などが多い傾向にありますが、近年は大手法人でも時短勤務や在宅勤務制度が整備されてきており、出産後もキャリアを中断せずに働く女性会計士も増加中です。
また、女性士業に特化した税務・会計のネットワークやコミュニティも存在し、女性ならではの共感力を活かして、相続相談や創業支援などで活躍している例もあります。
地方での独立事例
税理士・会計士の独立開業は、東京・大阪など都市部に限らず、地方都市や郊外エリアでも十分に成り立ちます。
特に税理士は、地域の中小企業や個人事業主とのつながりを活かし、「顧問契約」や「確定申告代行」「相続対策」などを安定的に受注できることが特徴です。地方では士業の競争も都市部に比べて激しくなく、地元密着の営業活動を地道に行えば、顧客からの信頼を得て長期契約につなげやすい環境にあります。
公認会計士についても、税理士登録をしたうえで地方の事務所を構え、監査業務と税務顧問を組み合わせてサービス提供している方も多数います。地元の金融機関や商工会議所と連携し、地域経済の活性化に貢献している例も多く、都市部での経験を活かして地元に戻って独立する“Uターン開業”の事例も増加中です。
年収・報酬の違いはある?|会計士・税理士の年収事情
公認会計士と税理士は、どちらも国家資格として高い専門性と信頼性を持っていますが、その報酬体系や年収レンジには明確な違いがあります。ここでは、それぞれの職種における平均年収や報酬形態について解説します。
公認会計士の報酬・年収
公認会計士は、勤務先や担当業務、経験年数によって年収に大きな幅があります。
監査法人勤務(スタッフ〜マネージャー):年収600〜1,000万円程度
監査法人のパートナー(共同経営者):年収1,500万円以上
一般企業のCFOや経理部長:年収800〜1,200万円
独立開業:案件次第で年収2,000万円以上も可能
特に監査法人のマネージャー職以上や、M&Aなどのアドバイザリー業務に携わる会計士は高収入となる傾向があります。加えて、語学力やITスキルを併せ持つ人材は、外資系企業やグローバル案件での高報酬が期待されます。
税理士の報酬・年収
税理士の報酬は、顧問先の数や業務内容、開業・勤務の別によって異なります。
税理士法人勤務:年収400〜800万円程度
資産税・相続税専門事務所勤務:年収600〜1,000万円前後
独立開業(小規模):年収500〜1,000万円程度
独立開業(成功例):年収1,500万円以上も可能
税理士は、定期的な顧問契約(月額1?10万円程度)を中心に、年末調整や決算・申告などのスポット業務を組み合わせて収益を上げるビジネスモデルです。特に相続税や資産税に強い税理士は、高額案件を扱うことが多く、1件で数十万?100万円超の報酬になるケースもあります。
報酬面から見たメリット・デメリット
公認会計士は、案件単価が高く、高年収を狙いやすい反面、激務やプレッシャーも大きい傾向がありますが多彩なキャリアパスからコンサル、事業会社、開業などがあり、働き方や求める報酬も選択肢が多いです。。一方、税理士も大手法人では高年収になりやすく、コンサルなどさらなる報酬を狙える選択肢もあります。また事務所開業から地道に顧問先を積み重ねることで安定した収入を得やすく、独立もしやすいのが特徴です。
会計士と税理士、どちらが将来性ある?
公認会計士と税理士はどちらも専門性の高い国家資格であり、今後もニーズが期待される職業です。しかし、テクノロジーの進化や社会構造の変化によって、求められる役割や活躍の場には違いが出てきています。
ここでは、それぞれの将来性について、業界動向や時代背景をふまえて比較します。
公認会計士の将来性|監査+経営視点が求められる時代へ
公認会計士の最大の強みは、監査という独占業務を有していることです。特に上場企業や金融機関では監査が法的に義務付けられているため、安定したニーズがあります。
また、近年では以下のような領域でも会計士の需要が高まっています。
M&Aや企業再生分野での財務デューデリジェンス
ESG(環境・社会・ガバナンス)開示や非財務情報の監査
スタートアップ企業へのCFO(最高財務責任者)就任
海外案件・外資系企業での会計監査対応(英語力が武器)
テクノロジーの進化によって「単純な会計処理」は自動化が進んでいますが、逆に高度な判断や専門知識が求められる業務の価値は高まっているため、会計士の将来性は引き続き高いといえるでしょう。
税理士の将来性|中小企業支援と資産税分野で安定ニーズ
一方、税理士はAIやクラウド会計ソフトの普及によって一部業務の自動化が進行していますが、以下のような分野では依然として高い需要があります。
中小企業の経営者に対する税務・経営サポート
相続・贈与などの資産税対策
創業支援・法人設立に伴う税務指導
事業承継・後継者対策のコンサルティング
特に高齢化が進む日本においては、相続・贈与に関する相談が年々増加傾向にあり、資産税に強い税理士は“選ばれる専門家”として活躍の場が広がっています。
さらに、中小企業向けのコンサルティング型税理士事務所も増えており、「記帳・申告」だけでなく、「経営改善」「補助金申請支援」なども担うことで、価格競争を避けた高付加価値型のサービスを展開しています。
会計士の転職ならムービンにご相談下さい
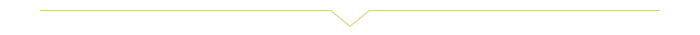
転職サービスはすべて無料となっております。
ムービンではお一人お一人に合わせた転職支援、そしてご自身では気づかれないキャリアの可能性や、転職のアドバイス、最新の情報をご提供致します。
- 29年以上の転職支援実績と圧倒的なノウハウ
- 会計士の方の主要転職先を網羅
- 過去1,000名以上の会計士キャリア支援
会計士の転職ならムービンにご相談下さい
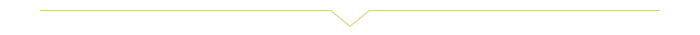
転職サービスはすべて無料となっております。
ムービンではお一人お一人に合わせた転職支援、そしてご自身では気づかれないキャリアの可能性や、転職のアドバイス、最新の情報をご提供致します。
- 29年以上の転職支援実績と圧倒的なノウハウ
- 会計士の方の主要転職先を網羅
- 過去1,000名以上の会計士キャリア支援
その他「会計士」転職事情・業界トピックス一覧

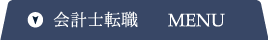
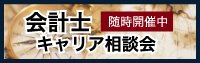
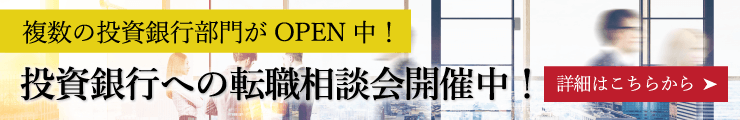
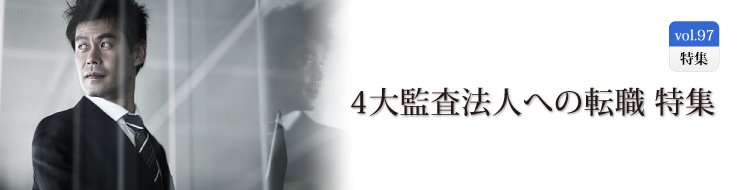

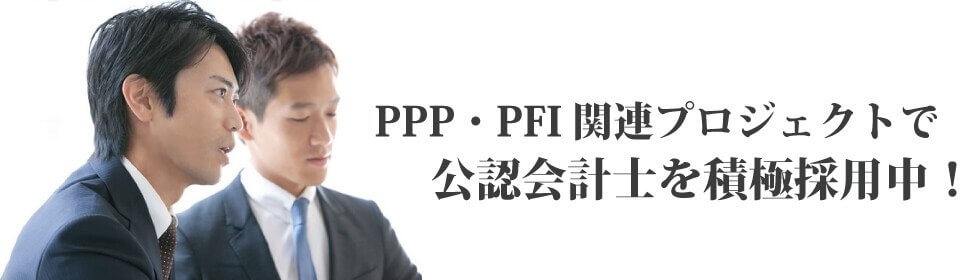
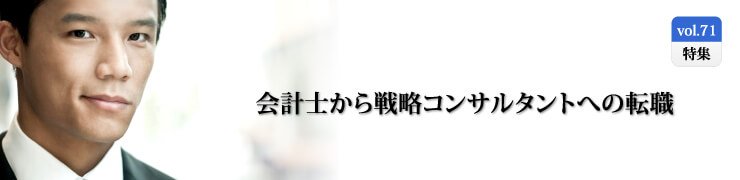
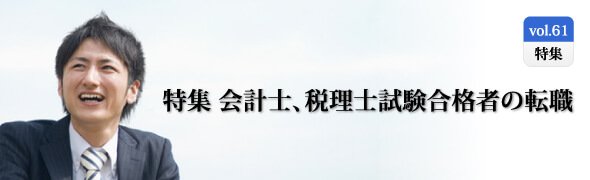
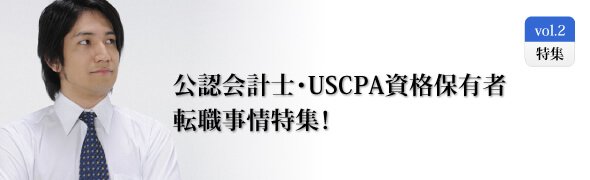

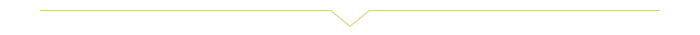
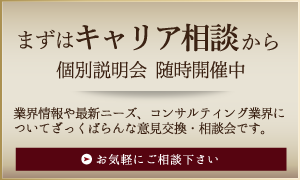
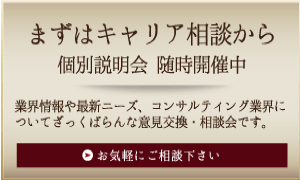








 初めての方へ - 転職を検討される金融業界の方へ【キャリアの考え方】
初めての方へ - 転職を検討される金融業界の方へ【キャリアの考え方】